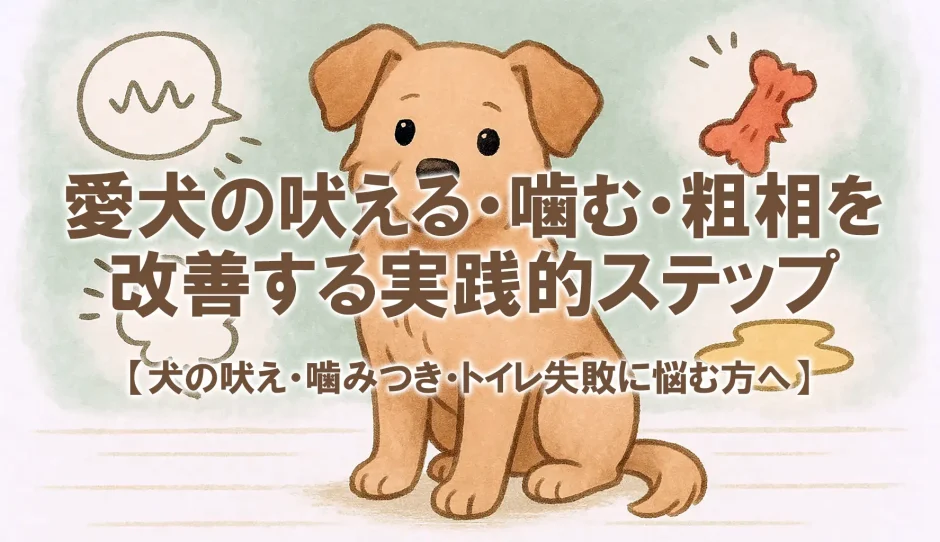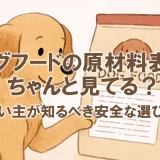なぜ犬は「困った行動」をするのか?根本原因を知ることが第一歩
愛犬の「吠える」「噛む」「トイレの失敗」といった行動に、頭を抱えている飼い主さんは少なくありません。私自身も犬を飼い始めた当初、思い通りにいかない場面に何度も戸惑いました。ただ、ひとつ確信しているのは、犬が“困った行動”をするのは、悪気があるからではないということです。
犬の行動には、すべて理由がある
犬の吠えは、感情の表現であり自己主張の一つ。警戒心、不安、要求、興奮など、その背景は多岐にわたります。また、「噛む」行動も攻撃性ばかりが原因ではありません。ストレスの発散だったり、相手との距離感を測る手段だったりと、人間の解釈だけで“問題”と決めつけるのは早計です。
トイレの失敗についても、単なるしつけ不足で片づけられがちですが、実は体調不良やマーキング、環境変化へのストレスが引き金になっていることも多いのです。行動そのものよりも、「なぜそれが起こったのか」を読み解く視点が欠かせません。
飼い主の反応が行動を助長しているケースもある
これは私自身の反省でもあるのですが、「吠えないで!」と大きな声で注意すると、それが犬にとっては「吠えれば飼い主が反応してくれる」と映ってしまうことがあります。噛まれたときに反射的に手を引くのも、「ああすれば相手が退く」と覚えさせるきっかけになります。
つまり、知らず知らずのうちに“問題行動”を強化してしまっている可能性があるのです。
まずは客観的に「いつ・どこで・なぜ」を記録する
困った行動を直したいなら、いきなり叱るのではなく、まずは冷静に観察することが大切です。具体的には、以下のような視点で記録をつけてみましょう。
- 吠えるのはどのタイミングか?(来客時?散歩の前?)
- 噛む対象に一貫性はあるか?(子ども?見知らぬ人?)
- トイレの失敗に共通する時間帯や状況は?
こうした“行動のクセ”を把握できると、原因が見えてくるケースは意外と多いものです。実際、私が飼っている犬も「留守番の直後に吠える」というパターンがわかり、対応を変えたことで落ち着きました。
犬の問題行動を解決するには、「行動だけを見て判断しない」ことが何より重要です。
次章では、特に悩みが多い「吠え」について、原因別に分けた具体的な対処法を掘り下げていきます。
愛犬の「吠え」に悩んでいる人へ——原因別・正しい対応法とは

犬の吠えは、単なるうるさい音ではありません。それは犬なりの言葉であり、サインです。私自身、最初は「静かにしてほしい」という思いだけで叱っていたことがありましたが、吠えの背景にある理由をきちんと知るようになってから、愛犬との関係性が変わりました。
ここでは、よく見られる吠えのタイプをいくつかに分類し、それぞれの原因と対処法を詳しく解説します。
① 警戒・防衛の吠え:インターホン、物音、通行人などへの反応
これは「不安」や「警戒心」から来る吠えです。インターホンが鳴ると吠える犬は非常に多いですが、それは「この家を守らなきゃ!」という本能的な防衛反応。特に神経質な犬や、社会化が不十分な犬によく見られます。
対処法:
- インターホンの音に慣れさせる“脱感作”トレーニング
- 吠える前に指示を出す(おすわり・マテ)
- 飼い主が落ち着いて行動する(不安は犬に伝染します)
私は、録音したインターホン音を使って毎日少しずつ再生する方法を取り入れました。最初は吠えても、根気よく繰り返すうちに反応が薄れ、今ではほとんど無視できるように。
② 要求吠え:遊んでほしい、ごはんがほしい、構ってほしい
「この行動をすれば、飼い主が反応してくれる」と犬が学習すると、吠えが習慣化します。これが要求吠えです。飼い主としては無視できない気持ちもわかりますが、一度でも応じてしまうと「吠え=成功体験」になってしまいます。
対処法:
- 吠えている間は絶対に反応しない(目も合わせない)
- 静かになった瞬間に褒める・ごほうびを与える
- 吠える前に欲求を満たす工夫をする(運動、知育玩具など)
我が家の犬は、以前は朝ごはんを催促して吠えることがありました。時間を決めて、吠えても出さない・静かに待てたらごはんというルールに変えてからは、自然と落ち着くように。
③ 分離不安による吠え:留守番中や姿が見えなくなると吠える
これは「ひとりになるのが怖い」という感情から来る吠えです。室内犬や甘えん坊な性格の犬に多く、長時間の留守番で悪化する傾向があります。外出のたびに吠えるようであれば、分離不安の可能性を疑ってみましょう。
対処法:
- 外出前のルーティンを無機質にする(声をかけずに出る)
- 帰宅時も騒がず自然体で(大げさなリアクションはNG)
- 短時間の留守番から徐々に慣らす
実際、私の愛犬もはじめは外出直後に吠えていましたが、“帰ってくるから大丈夫”という信頼感を育てることで徐々に吠えは減っていきました。
吠えるという行動は、飼い主との信頼関係や日常の過ごし方に大きく関わっています。問題に見えても、視点を変えれば犬からの“メッセージ”。それを正しく受け取ることで、吠えはコントロール可能になります。
次章では、「噛む」という行動に焦点を当て、子犬・成犬・高齢犬それぞれに多い原因と対応策をお伝えします。
「噛む」行動の背景と、成長段階ごとの対処法

犬に噛まれると、単なるケガ以上に、信頼関係が崩れてしまったような気がしてショックを受けることがありますよね。私も初めて噛まれたときは、「どうして…?」としばらく落ち込みました。ただ、あとから冷静に振り返ると、その行動にもちゃんと理由があったことに気づかされます。
噛む行動には、恐怖・興奮・ストレス・成長過程…とさまざまな背景があります。つまり、噛まれた瞬間の行動だけに注目するのではなく、「なぜそうなったのか」という流れに目を向ける必要があるのです。
ここでは、子犬・成犬・シニア犬と、それぞれの段階で見られる“噛みたくなる理由”と、その対処法を解説します。
子犬編:甘噛みは「学習中の証」
生後数ヶ月の子犬がやたらと何でも噛みたがるのは、好奇心と歯の生え変わりが理由です。これはある意味、「人間でいう幼児のなんでも口に入れたがる時期」と似ています。
ただ、問題は“人の手”を噛むことをそのまま放っておくと、それが習慣になってしまう点にあります。
私の対処法:
- 「ダメ」と声を荒げず、噛まれた瞬間に静かに手を引き、目も合わさない
- 代わりに噛んでよいおもちゃをすぐに渡し、「こっちはOK」と教える
- 手にじゃれてきたら、遊びを一時中断することで「それをすると楽しいことが終わる」と理解させる
大切なのは、「怒らず、でも一貫してルールを伝える」ことだと実感しています。
成犬編:ストレスと感情の爆発に注意
成犬が噛むと、「性格の問題なのでは」と不安に思うかもしれません。けれど、よく観察していると、噛む前には必ず“予兆”があることがわかります。例えば、唸る、身体がこわばる、目をそらさずに見てくるなど…。こうしたサインを見逃さないことが、トラブル回避の第一歩です。
考えられる原因:
- 無理に体を触られた(特に耳や尻尾など敏感な部分)
- 興奮状態で制御が効かなくなった
- 食事中の接近や、守りたい物(おもちゃなど)への介入
私が効果を感じた対処法:
- 「嫌がるサイン」が出たら距離をとるクセをつける
- 食事中は手を出さず、落ち着いたあとで接近する
- 触られる練習は1日数秒から始めて、徐々に慣らしていく
犬との関係性が深まると、「今日は触っても大丈夫そうだな」という空気が読めるようになります。これは一朝一夕には築けないものですが、信頼があると噛むリスクは確実に減ります。
シニア犬編:年齢による変化を見逃さない
高齢の犬が突然噛むようになるケースでは、体の痛みや加齢による認知機能の変化が関わっていることが多いです。私も、以前まで穏やかだったシニア犬に噛まれたとき、「性格が変わったのかな?」と心配しましたが、実際は関節の痛みが原因でした。
シニア犬の噛み対策:
- まずは獣医師に相談し、身体の異常がないか確認する
- 触られることに過敏になることを想定し、スキンシップの頻度や方法を調整する
- 日常生活でストレスを減らし、安心できるルーティンを作る
高齢犬にとって、急な刺激や環境の変化は非常に大きな負担になります。若い頃と同じように接しようとせず、「今のこの子にとって心地よい距離感」を大事にしたいですね。
噛むという行為には、「やめさせたい!」と思う感情がついて回ります。ですが、それは犬なりのSOSや、理解してほしいというサインでもあると考えた方が、より建設的です。叱って封じ込めるのではなく、冷静に、そして根気よく向き合うこと。それが、飼い主としての信頼を深める一歩だと私は感じています。
次章では、トイレの失敗、いわゆる“おしっこ問題”について、具体的な解決策と見落としがちな落とし穴に触れていきます。
おしっこ問題の本質と、トイレの失敗を減らすための見直しポイント

犬の「おしっこトラブル」は、意外にも多くの飼い主が直面する悩みのひとつです。特に、室内飼いの犬にとってトイレの習慣づけは生活の土台となる部分。それだけに、一度つまずくと「叱る」「我慢する」の悪循環に入りがちです。
私も以前、トイレトレーニングがなかなか定着せず、「どうしてうまくいかないんだろう?」と何度も悩みました。でも、ある視点の変化がきっかけで、解決の糸口が見えてきたんです。
ここでは、トイレの失敗が起きる背景と、効果的な対処法を詳しく解説していきます。
よくあるトラブル①:「場所が覚えられない」
一番多いのは、「トイレの場所は教えたのに、なぜか違う場所でしてしまう」というケース。これは、場所の記憶が曖昧だったり、そもそも覚える条件が整っていない可能性があります。
確認したいポイント:
- トイレシートの場所が頻繁に変わっていないか
- 匂いが残っていて、犬が「そこはトイレだ」と思い続けていないか
- そもそも、犬にとって“そこが安心して排泄できる空間”かどうか
私は、トイレの位置を部屋の隅から窓際に移しただけで成功率がぐっと上がった経験があります。意外と**「人の目が気にならない場所」**というのは、犬にとっても大事なんです。
よくあるトラブル②:「トイレはできるけど、マーキングする」
マーキングは、オス犬だけでなくメス犬にも起こります。「ここは自分の場所」と主張したいという本能的な行動で、特に新しい環境や来客があったときに起こりやすいのが特徴です。
対応のポイント:
- 発生しやすいタイミングを観察し、事前にリードや指示でコントロール
- 去勢・避妊の有無が影響している場合もあるので、獣医と相談
- 匂いが残ると再発しやすいため、専用の消臭スプレーで徹底的に拭き取ること
私の場合、来客のたびにカーテンにマーキングしてしまう時期がありました。対策として、来客前に軽く散歩をさせて排尿させておくことで、だいぶ落ち着きました。
よくあるトラブル③:「留守番中だけ失敗する」
普段はきちんとできているのに、留守番中だけ粗相するという場合は“分離不安”の可能性もあります。寂しさや不安から、トイレとは関係ない場所で排泄することでストレスを発散しているのです。
対策として有効な方法:
- 留守番の時間を少しずつ伸ばす練習をする
- 知育トイ(フードが出るおもちゃ)などで不安を紛らわせる
- 飼い主の帰宅時も騒がず自然にふるまう(構いすぎない)
うちの犬も、出かけると決まって玄関前でおしっこをしていました。それが「帰ってきて」というサインだったことに気づいてからは、出かける前に特別な挨拶をせず、淡々と出ていくように変えたことで徐々に改善しました。
トイレのしつけに必要なのは「根気」と「観察力」
トイレの失敗が続くと、「もう無理かも…」と感じてしまうこともあるかもしれません。でも、叱っても逆効果になることが多いのがこのトピックの難しさです。
大切なのは、犬が“成功しやすい状況”をこちらが丁寧に整えてあげること。失敗を怒るのではなく、成功を強化する。その積み重ねが、一番の近道だと私は実感しています。
次章では、「こうした困った行動をどう予防するか?」という視点から、日々の接し方や習慣の中で意識したいポイントを紹介していきます。
困った行動を未然に防ぐために——日常の習慣で変わる犬の行動

ここまで「吠える」「噛む」「おしっこの失敗」といった代表的な困りごとの原因と対処法を見てきましたが、実際のところ、一番大切なのは問題が起こる前に“予防する”意識を持つことだと私は感じています。
犬の行動には“突然”はありません。必ず、日々の環境や関わり方の中に原因となる小さな積み重ねがある。つまり、普段からの接し方がそのまま犬の行動に現れているのです。
この章では、困った行動を予防するために、日々の暮らしの中で意識したい習慣やポイントをお伝えします。
1. 「注目される行動」が習慣化されると心得る
犬は非常に賢く、人の反応を敏感に読み取ります。たとえば、「吠えたら飼い主が近づいてくれた」「粗相したら大声を出してくれた」——このような**“注目される体験”は、行動を強化する材料になってしまう**のです。
私も以前、愛犬のいたずらをつい慌てて止めたことがありました。すると、そのリアクションが面白かったのか、余計に同じことを繰り返すように…。それからは、「望ましい行動をした時だけ、しっかり褒める」を徹底するようにしました。
ポイント:
- 吠えた時や粗相をした時に過剰に反応しない
- 「静かにしていたら褒められる」ことを教える
- 問題行動ではなく、“良い行動”を見逃さずに強化する
2. 心と体が満たされているか、毎日のチェックを
犬の問題行動は、「退屈」「ストレス」「運動不足」「孤独」などのフラストレーションが原因になっていることが非常に多いです。
散歩の時間や回数だけでなく、「匂いを嗅がせる自由な時間」「ゆったり過ごす静かな時間」など、心の充足感も日常に必要です。私は、決まった散歩コースをあえて外し、新しいルートを歩くようにしてから、犬の表情が変わったのを実感しました。
日々意識したいこと:
- 運動量は足りているか(犬種によって大きく異なる)
- ストレスを感じる環境になっていないか(音、人間関係など)
- 飼い主との関係が「指示」ばかりになっていないか
3. 一貫性と安心感がある暮らしをつくる
犬は「変化」が苦手な生き物です。だからこそ、ルールや対応が毎回違うと混乱し、結果として不安定な行動につながってしまいます。
私も反省したことがあります。ある日は「おすわり」と言って待たせていたのに、別の日には言わずにおやつを与えてしまったり…。その結果、指示が曖昧になり、犬が戸惑うことに。
安定した環境のためにできること:
- 家族全員でルールを共有する(トイレ、散歩、食事のタイミングなど)
- 指示語を統一する(例:「おいで」or「カム」など混乱させない)
- 生活の流れに一定のリズムを持たせる(散歩や食事の時間帯など)
犬との暮らしは“育て合い”の関係
犬に「しつける」というと、どうしても“上下関係”や“支配・服従”というイメージがつきまといがちですが、私はそうではないと思っています。むしろ、**犬と飼い主が互いに信頼を深めながら“育て合っていく”**関係性のほうが、自然でしっくりくるのです。
困った行動を責めるよりも、「なぜそうなったのか?」を一緒に考える。その姿勢が、結果的に問題行動を減らす一番の近道になるのだと、私自身が経験を通して感じています。
次章では、この記事のまとめとして、犬と向き合う中で私が学んだこと、伝えたい思いを綴ります。
愛犬と向き合うことで見えてきた、本当の信頼関係とは

「吠える」「噛む」「トイレの失敗」——どれも飼い主にとっては悩ましい行動です。私も初めて犬を迎えたときは、理想と現実のギャップに戸惑い、何度も「自分には無理なんじゃないか」と落ち込みました。
けれども、試行錯誤を重ねていくうちに、少しずつわかってきたことがあります。
それは、犬の問題行動は“犬のせい”ではなく、“関係性の中で起きているサイン”だということです。
「問題行動」を通して、飼い主も成長する
犬が何かを伝えようとしているとき、それがたまたま人間にとって困った形で現れる——それだけの話です。そこに意味づけをして、「悪い子だ」「わがままだ」と決めつけてしまえば、犬との間には壁ができます。
私自身、「吠えるたびに理由がある」「噛む前にサインが出ている」「粗相にも感情が絡んでいる」と気づいてから、見える世界が変わりました。犬に教えているつもりで、実は自分が教えられていた。そんな瞬間の積み重ねが、信頼関係をつくっていくのだと思います。
大切なのは、完璧な「しつけ」ではなく、心の余白
インターネットや本には、しつけの正解がたくさん並んでいます。でも、実際には犬の性格も、家庭環境も、飼い主のスタンスも千差万別。だからこそ、「こうしなければいけない」と思いすぎないことも大切です。
たとえ失敗しても、一歩ずつ犬と歩調を合わせていければ、それで十分。正しさを追い求めすぎてギスギスするよりも、**“ちょっと不格好でも笑って過ごせる日々”**の方が、犬にとっても飼い主にとっても、ずっと心地よいのではないでしょうか。
最後に:犬は言葉を持たない。でも、伝えてきている
犬は言葉を話さない代わりに、表情や動き、鳴き声、仕草ですべてを伝えようとしてくれています。そのサインを丁寧に拾い、寄り添う努力を続けること。それこそが、犬と暮らす私たちができる最も誠実な向き合い方だと私は信じています。
困った行動は、「問題」ではなく「コミュニケーションの入り口」。そう考えられるようになったとき、きっとあなたと愛犬の関係は、もう一段深まっているはずです。
この記事が、犬との暮らしに悩む誰かの背中をそっと支える一助となれば嬉しいです。
無理なく、焦らず、ひとつひとつの瞬間を大切に——それが、愛犬との毎日をより豊かにしてくれる鍵だと、私は信じています。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。