犬が吠えるのは「悪いこと」ではない。まずは原因を見極める
「無駄吠え」と一言で片付けてしまうと、あたかも犬が“意味もなく騒いでいる”ように思えてしまいます。しかし、私たち人間が何かを伝えたいときに声を発するのと同じように、犬も吠えることで何かを伝えようとしているのです。
私が初めて犬を飼ったとき、玄関のチャイムに過敏に反応して吠える様子に戸惑いました。最初は「うるさいな」と感じたものの、次第にその行動の裏にある「不安」や「警戒心」に気づき、叱るのではなく“理由を探す”ことの大切さを知りました。
犬が吠える主な理由とは?
犬が吠える理由は、決して一つではありません。たとえば以下のようなパターンがあります:
- 警戒・防衛本能
見知らぬ人や音に反応するのは、縄張りを守ろうとする本能的な行動です。特に来客時や外の物音に過敏な犬ほど、こうした吠えが目立ちます。 - 不安・孤独からの訴え
長時間の留守番や環境の変化によって不安を感じると、犬はその感情を吠えることで表現することがあります。これは「誰か気づいて」「ひとりにしないで」というサインでもあります。 - 要求行動としての吠え
「遊んで」「おやつちょうだい」など、何かを求めているときに吠える犬も少なくありません。要求に応えてしまうと、その行動が強化されてしまうことがあります。 - 刺激不足・退屈
特に活発な犬種では、身体を動かす機会が少ないとエネルギーを持て余して吠えることがあります。これは単なる癖ではなく、心身のバランスが崩れているサインかもしれません。
吠え方で犬の気持ちは変わる
犬の吠え方は一様ではなく、声の高さ、長さ、間隔などに微妙な違いがあります。私自身、「短く甲高い吠え=何か要求している」「低く唸るような吠え=警戒している」といった具合に、愛犬の声を少しずつ聞き分けられるようになりました。これは、日々向き合っているからこそ分かる“犬との会話”なのだと感じています。
犬が吠えるのは「問題行動」ではなく、「何かを伝えたいという表現」です。その背景にある気持ちを読み取り、適切な対応をとることが、無駄吠えを減らす第一歩です。
次章では、私たち飼い主の“リアクション”が知らず知らずのうちに吠えを強化してしまっている可能性について、掘り下げていきます。
知らずに強化してしまう「飼い主のリアクション」

無駄吠えの対策を考えるとき、多くの人が「どうすれば犬を黙らせられるか」という視点に偏りがちです。けれど実際には、「吠える行動を飼い主が知らずに強化してしまっている」ケースがとても多いのです。
私も過去に、愛犬が吠えるたびに「静かにして」と声をかけたり、おやつを渡したりしていました。今思えば、それが“ご褒美”になっていたのです。
犬にとっての「リアクション」はすべて学習材料
犬は、行動の後に起こる出来事から「これは良かった」「これは意味がなかった」と学習します。
たとえば、吠えた直後に飼い主が近づいてきて話しかけたとしたら、犬は「吠えたら構ってもらえる」と思い込みます。それがたとえ叱る言葉だったとしても、犬にとっては“注目されること”自体が報酬になることがあるのです。
よくある“逆効果”の対応例
- すぐに声をかける/抱っこする
「大丈夫だよ」と言いたい気持ちはわかりますが、それが“吠えた結果、構ってもらえた”という認識につながる可能性があります。 - 大声で叱る
怒鳴ることで犬がさらに興奮し、「飼い主も吠えている」と錯覚することすらあります。これでは状況が悪化しかねません。 - おやつやおもちゃを与えて黙らせる
一時的には静かになるかもしれませんが、「吠えたらいいことがある」という誤った学習につながるので、根本的な解決にはなりません。
本当に効果のある対応とは?
- 完全に無視する
要求吠えの場合、目を合わせず、声もかけず、立ち去ることで「吠えても意味がない」と学ばせます。最初は吠えが一時的に激しくなる“消去バースト”が起きるかもしれませんが、根気よく続けることが肝心です。 - 静かになった瞬間を逃さず褒める
吠えやんだタイミングで優しく声をかけたり、ご褒美を与えることで、「静かにしている=良いことがある」と結びつけます。 - 一貫した対応を全員で共有する
家族全員が同じ対応を取ることがとても重要です。誰か一人でも異なる対応をすると、犬は混乱して学習が進みません。
無駄吠えをやめさせるには、犬の行動そのものだけでなく、それを見た人間側の反応がどう影響しているかを見直す必要があります。「吠えるから怒る」のではなく、「吠える前の対応」「吠えた後の反応」まで、丁寧に見直すことが改善のカギです。
次章では、犬のストレスや安心感に直結する「環境づくりと運動量のバランス」についてご紹介します。
犬が安心できる空間をつくる。それが無駄吠えを減らす本当の近道

「吠える」という行動だけに目を向けてしまうと、つい“止める方法”ばかり探してしまいます。けれど本当は、犬が“吠えざるを得ない状態”を作ってしまっているのは、私たち人間側の環境や接し方だったりするんですよね。
私も昔、愛犬の吠えが気になりすぎて、コマンド練習や無視のテクニックばかり試していました。でもあるとき、「この子は安心できていないんじゃないか」と思い至ったんです。
吠えやすい環境には、必ず“落ち着けない要素”がある
たとえば家の中。人の出入りが激しい場所や、外の音が響きやすい場所に犬の居場所があると、それだけで緊張が続きます。
「なんでこんなに吠えるんだろう?」と悩んでいた当時、私は愛犬の寝床を窓際から部屋の奥の静かな場所に移したんです。たったそれだけで、来客時の吠え方が明らかに変わったんですよね。
- 外の景色が刺激になっていないか?
散歩中の犬や通行人、車の音など、外から入ってくる情報は想像以上に犬を刺激します。見せない・聞かせない工夫は、決して“閉じ込める”ことではなく、「休ませてあげる」ための配慮です。 - 安心できる“巣”を用意してあげる
クレートや毛布、囲まれた空間など、犬にとって安心できるスペースがあると、「守られている」という感覚を持てるようになります。それが結果として、不要な警戒吠えを減らすことにつながるのです。
運動不足は“静かな不満”の積み重ね
運動量についても、ただ散歩に行っていれば大丈夫、というわけではありません。
特に気をつけたいのが「動くけど満足してない」状態です。
以前の私も、朝と夕方に短めの散歩をして「これでOK」と思っていました。でも、帰ってきてからも部屋の中を落ち着きなく歩き回ったり、わけもなく吠えたりすることが続いて、ようやく気づいたんです。「この子、全然満足できてないな」って。
- 距離より“内容”が大事
同じコースをただ歩くだけでは、犬にとっては退屈なルーティンです。においを嗅がせたり、ちょっと寄り道したり、五感が刺激される体験を取り入れることで、犬は「今日は充実してたな」と感じるようになります。 - 頭を使う遊びも侮れない
室内でできる“探す遊び”や知育トイを活用すると、エネルギーを発散できるだけでなく、満足感も得られます。「疲れさせる」より「納得させる」ことを意識してみてください。
“吠える”前に、気持ちを落ち着ける環境を
吠える行動は、犬からの「もう限界だよ」のサインかもしれません。
わたしたち人間だって、ストレスが溜まっているときほど、些細なことに反応しやすくなりますよね。犬も同じです。
だからこそ、まずは“落ち着ける空間と時間”を整えてあげる。それが、無駄吠えを減らす一番の土台になると私は感じています。
次章では、環境を整えた上でどう「伝えるか」――つまり、基本的なコマンドや切り替えのテクニックについて詳しく解説します。
コマンドは“しつけ”ではなく“会話”。行動を切り替えるトレーニングのすすめ
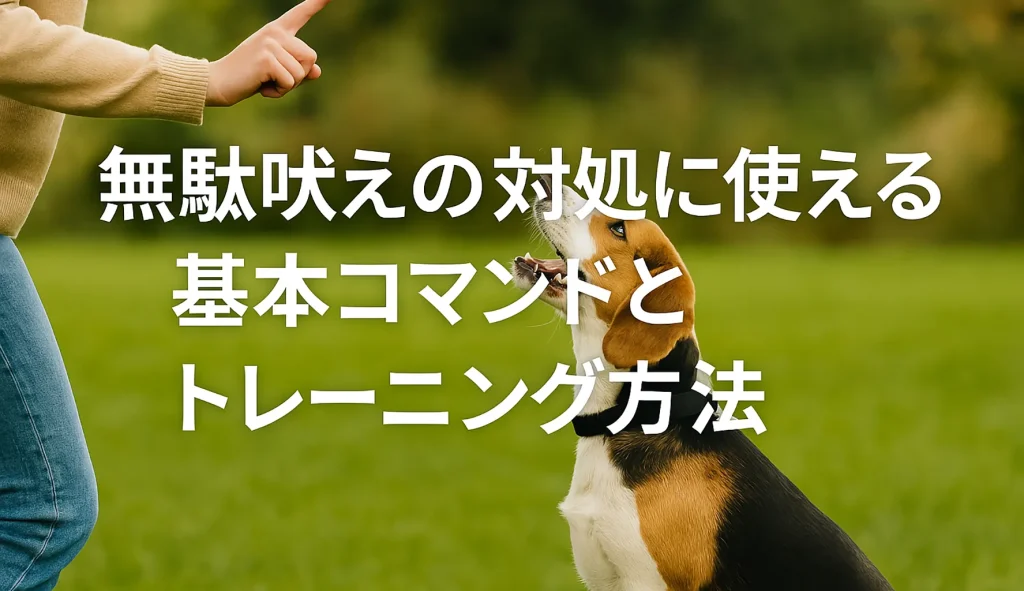
「静かにして」「ダメ」「おすわり」——。犬に言葉をかけることは日常的ですが、果たしてその言葉、本当に犬に“伝わって”いるでしょうか?
私がこの疑問にぶつかったのは、何度「やめて」と言っても吠え続ける愛犬を目の前にしたときでした。叱っても、なだめても、状況は変わらない。結局、伝え方の“中身”が間違っていたんだと、後になって気づきました。
コマンドは「行動の切り替え」を教えるツール
犬にとって、“吠えるな”は抽象的すぎます。代わりに「じゃあ何をすればいいの?」がわからないと、ただ混乱するだけです。
そこで必要なのが、「吠える代わりに取るべき行動」を明確に教えること。つまり、コマンドは「してほしいことを具体的に示す言葉」なんです。
有効な基本コマンドの例:
- おすわり・ふせ
興奮しているときに姿勢を落ち着かせるコマンド。特に“ふせ”は自然と呼吸もゆっくりになり、気持ちを落ち着けやすくなります。 - まて
来客時やチャイムが鳴ったときなどに、次の行動を抑えるための合図として有効。自分をコントロールする練習にもなります。 - しー・静かに(オリジナルでもOK)
吠えるのをやめさせたいときの合図に使う言葉。最初は吠えていないときに声をかけ、落ち着いた状態を褒めることで意味を学ばせます。
トレーニングで大切なのは「タイミング」と「温度感」
犬にとって、行動と報酬が結びつくのはほんの数秒のあいだ。
だからこそ、吠えるのをやめた“瞬間”に褒める・ご褒美を与えることがとても重要です。「静かになったね」と落ち着いた声で伝えるだけでも、十分に効果があります。
一方で、トレーニングに焦りや怒りが混ざると、それは犬にとって“混乱のサイン”になります。
声を荒げる必要はまったくありません。むしろ、**落ち着いた声・落ち着いた動作こそが、犬に安心を与える“しつけの土台”**になります。
「できた」よりも「一緒にやった」が犬の自信になる
私がトレーニングを続ける中で感じたことは、犬は“正解”を探しているのではなく、“飼い主と気持ちが通じた瞬間”を求めているということです。
コマンドを覚えることはゴールではなく、「あなたと一緒に何かをやって楽しかった」という経験が、犬にとっての最大のご褒美になります。
次章では、吠えの根本的なきっかけとなりやすい「外部刺激」——とくに社会化の重要性と、どうすれば慣れていけるのかについて解説します。
社会化は“安心する力”を育てる。吠えにくい犬になるための経験の積み方

「知らない人を見て吠える」「犬同士のすれ違いで毎回パニック」「音に敏感で反応が激しい」——こうした行動の根っこにあるのは、多くの場合“慣れていない”という事実です。
社会化とは、「さまざまな刺激に触れ、これは怖くないと学ぶプロセス」。この段階をうまく経験できなかった犬は、未知のものに対して“吠えることで距離を取ろうとする”ようになります。
私も昔、保護犬を迎えたとき、通行人や自転車に対していちいち吠えるその様子に「なぜこんなに神経質なんだろう」と悩んだことがありました。でも、ある日「この子は、ただ“知らないもの”にどう対処すればいいか知らないだけなんだ」と思い至ったことで、アプローチが変わったのです。
社会化とは「刺激に慣れる練習」である
よく“社会化は子犬期だけが大事”と思われがちですが、成犬になってからでも十分にトレーニングは可能です。ただし、無理やり慣れさせようとするのは逆効果。ポイントは、“怖がらせない距離”と“成功体験の積み重ね”です。
慣れのステップの一例:
- 遠くから見せる
人や犬、自転車などの“吠えの対象”が現れる場面で、反応しない程度の距離から観察させます。吠えなければ褒めて、おやつを与える。 - 少しずつ距離を縮める
日を追って少しずつ距離を近づけていきます。吠えそうな兆しがあれば無理せずその日はそこで終了。 - 相手が通り過ぎる体験を増やす
「気にしなくても大丈夫だった」という経験が重なると、犬の中に“安心の蓄積”が生まれます。これが大切なんです。
社会化不足のサインは日常の中にある
- 知らない人を警戒して吠える
- 音に対して過剰に反応する(雷、チャイム、車)
- 他の犬と接すると興奮や恐怖でコントロール不能になる
こうした反応は、「知らないこと=危険かもしれない」と認識している証拠。逆に言えば、“経験”によって変えていけるものです。
飼い主が“落ち着いている”というメッセージを送る
社会化を進める上で意外と見落とされがちなのが、飼い主の表情や態度。私が身をもって感じたのは、自分が緊張してリードを握りしめているときほど、犬も周囲に敏感になっていたことです。
「怖くないよ」という言葉よりも、飼い主が堂々と落ち着いていることの方が、何倍も犬に伝わります。社会化とは、犬だけでなく、飼い主の心構えも一緒に育てていくものだと思っています。
次章では、吠えやすい場面として多くの飼い主が直面する「来客やチャイムへの反応」をどうコントロールするかを、具体的な方法とともに解説します。
チャイムで吠える、来客に吠える——“お決まりのパターン”から脱する具体策
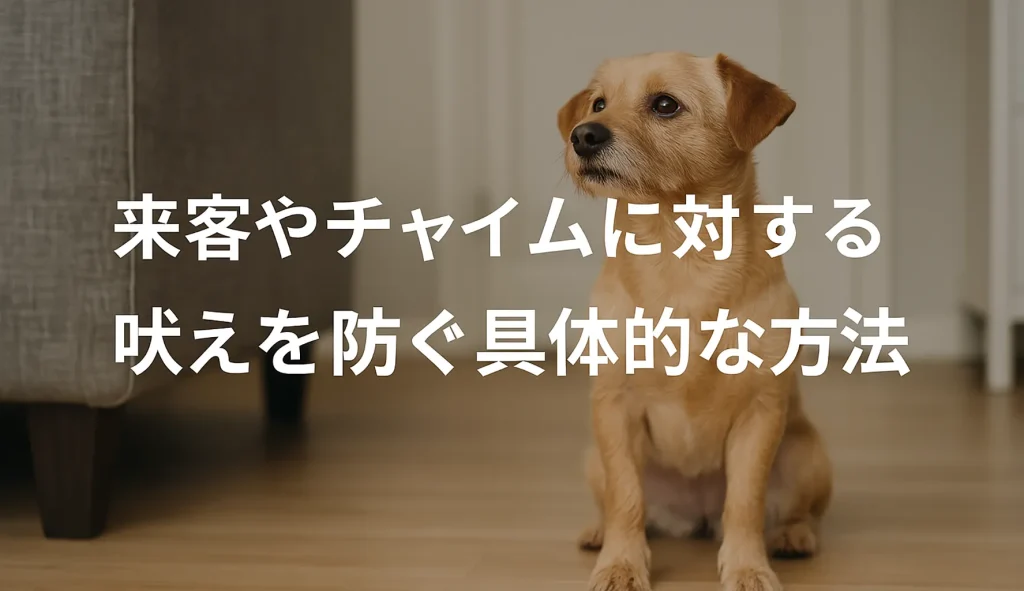
玄関のチャイムが鳴ると、犬が真っ先に吠え出す。来客が部屋に入ると、興奮して止まらない。
この“お決まりのパターン”に心当たりのある飼い主さんは多いと思います。かく言う私も、来客のたびに慌てて犬を抱え、話もままならない状況を繰り返していました。
でもあるとき、ふと「この流れを犬は“覚えてしまっている”のでは?」と気づいたんです。つまり、チャイム=吠える、来客=大騒ぎ、という反射的な反応を、生活の中で条件づけてしまっていたんですね。
チャイム=良いこと、という認識に塗り替える
犬は音や状況に“意味”を結びつけて行動します。だから、チャイムが「警戒するべき合図」ではなく、「落ち着いていれば褒められるもの」だと理解できれば、反応は大きく変わっていきます。
ステップ式の慣らし方
- チャイム音を録音して、日常の中で再生
本番は刺激が強すぎるので、まずは録音したチャイム音を小さな音量で流します。犬が吠えなければすぐにご褒美。これを繰り返すことで、「音が鳴っても、なにも起きない」状態に慣れていきます。 - 「チャイム→おすわり」のルーティン化
音が鳴った瞬間に「おすわり」などのコマンドを出し、行動を切り替えさせます。うまくできたら大げさなくらい褒めて、ご褒美を与えることで、正しい反応が“得になる行動”として定着します。 - 実際の来客対応をリハーサル
家族や友人に協力してもらい、実際の来客を想定した練習をします。段階的に距離を縮めて、最初はリビングに入れない設定で慣らしていくと、犬も徐々に安心できるようになります。
来客時の定位置を決めておく
私が試して特に効果を感じたのは、「来客時はここにいようね」と犬に“定位置”を教えたことです。そこはクレートでもソファの横でも構いませんが、“自分の安心できる場所”があると、犬は吠えることよりも落ち着くことを優先するようになります。
最初の数回は誘導が必要かもしれませんが、回を重ねるうちに、チャイムが鳴ると自分から定位置に向かうようになります。これは本当に感動しました。
来客にも協力してもらう
犬にとっては「知らない人が自分のテリトリーに入ってくる」のは当然の脅威です。
ですから、来客には「目を合わせない」「静かに振る舞う」などの配慮をお願いするのも有効です。無理に触れようとせず、犬が落ち着くまで距離を取ってもらいましょう。
“いつも同じ場面で吠える”というのは、犬が学習してしまった結果です。裏を返せば、「吠えないという選択」もまた、新しい習慣として学ばせることができるということ。
次章では、ここまで試してもうまくいかないときに頼るべき、“専門家の力”と“補助アイテムの活用法”についてご紹介します。
どうしても吠えが直らないとき——専門家と補助アイテムを味方にする

無駄吠えに向き合っていると、「いろいろ試したけど、もう限界かも…」と心が折れそうになることがあります。
私自身もそうでした。環境を整え、コマンドを教え、社会化にも取り組んで、それでもなお吠え続ける——そんなとき、私は自分を責めそうになりました。
でも、ふと思ったんです。“ひとりで頑張る”ことが偉いわけじゃない。
むしろ、“助けを求める勇気”こそが、飼い主として大切なことなんじゃないかと。
専門家に頼るのは“あきらめ”ではなく“前進”
ドッグトレーナーや動物行動学の専門家に相談することで、自分では見えていなかった犬の行動の背景が見えてくることがあります。
実際、私が相談したトレーナーの方は、うちの犬の吠え方とその前後の仕草から、「これは不安から来てる吠えですね」とすぐに見抜いてくれました。驚くほど腑に落ちました。
専門家がしてくれること
- 吠えの種類と原因の切り分け
- 飼い主の対応の癖やパターンの分析
- その犬に合った環境調整とトレーニングメニューの提案
- 必要があれば行動療法や医療的アプローチとの連携
自分では気づけなかった視点を与えてくれる、まさに“外側からの目”です。
補助アイテムは“コントロール”ではなく“サポート”
最近は、無駄吠え対策グッズも多様化しています。でも、使い方を間違えると、かえって犬にストレスや混乱を与えてしまうことも。
私が実際に使って効果を感じたのは、**バイブレーション首輪(刺激ではなく振動で注意を促すタイプ)**でした。吠えた瞬間に小さな振動があるだけで、うちの犬は「ハッ」と我に返るような反応を見せるようになりました。
ただし、これはあくまで吠える前に気づかせる“きっかけ”のツールであって、吠え自体を無理に止めるものではありません。
使い方のポイント:
- 事前に獣医やトレーナーと相談して導入する
- アイテムに頼りすぎず、同時に正しい行動を褒めて教える
- 犬が「怖い」と感じないよう、優しく短時間から慣らす
また、クレートや安心スペースの設置、知育トイによる気晴らしなども、吠えの頻度を減らすための大きな助けになります。
飼い主が「頼っていい」と思えること
私がいちばん伝えたいのは、「手に負えない」状況に対して、自分を責めなくていいということ。
専門家や道具に頼ることは、決して“諦め”ではありません。むしろ、それは犬にとっても、あなたにとってもより穏やかで幸せな関係を築くための一歩です。
次章ではいよいよ最終章。ここまでの取り組みをどう“続けていくか”、そして飼い主としてどんな心構えが必要なのかを、私自身の経験も交えてお話しします。
無駄吠え対策は「続けること」がすべて。焦らず、比べず、犬と一緒に歩むために

無駄吠えの対策には、近道も、正解も、たったひとつの方法もありません。
ある日突然ピタッと吠えなくなるわけでもないし、「これをやれば完璧!」なんて魔法のトレーニングも存在しません。だからこそ、この章では“続けるための心構え”について、私自身の経験をもとにお話しさせてください。
成功よりも、「昨日より一歩マシ」くらいの視点で
私も何度もくじけそうになりました。うまくいった日があったと思えば、翌日はまた振り出しに戻る。
それでも、「今日はチャイム音に2回しか吠えなかった」「吠えた後の切り替えが早くなった」——そんな小さな変化を見逃さないように意識し始めたら、不思議と気持ちが楽になったんです。
トレーニングは**“結果”より“過程”が大事**です。吠えなかった日より、「なぜ吠えなかったか」を一緒に積み重ねていく。その時間こそが、犬との絆になっていくのだと思います。
飼い主の気持ちが伝わるからこそ、“自分を整える”
犬は本当に繊細で、私たち人間の“声のトーン”や“表情の温度”を敏感に感じ取っています。
私がイライラして「また吠えた…」とため息をついていたとき、犬も不安そうな顔をしていたのを今でも覚えています。
「今日もうまくいかなくてもいいや」くらいの心の余裕が、犬にとっても安心材料になります。無駄吠えをやめさせるには、まずは飼い主が“落ち着いている存在”であることが、何よりの土台になると私は実感しています。
他人と比べない。SNSと距離を置くのもひとつの選択
ネットを見ると、「うちの犬は一週間で無駄吠えがなくなりました!」なんて成功談がたくさん出てきます。
でも、それはあくまで“その子とその環境の話”。焦る必要なんて、どこにもありません。
私もある時期、SNSから距離を置きました。他人のペースと、自分の犬との関係を重ねてしまいそうだったからです。
今思えば、それはとても大事な選択だったと思っています。
吠えは「困った行動」じゃなく、「つながるための入り口」だった
無駄吠えに向き合ってきて、私はようやく気づいたんです。
吠えるという行動の裏には、犬の“何かを伝えたい気持ち”が常にあるということ。
それにちゃんと向き合おうと決めたときから、犬との関係は少しずつ変わっていきました。
だから、もし今あなたが「うちの子、どうしてこんなに吠えるんだろう」と悩んでいるなら、どうかすぐに“問題行動”と決めつけないでください。
その声の奥には、きっとあなたにしか気づけない何かがあるはずです。
無駄吠え対策の本当のゴールは、“吠えなくなること”ではなく、“吠えなくても安心して過ごせるようになること”。
そのための一歩を、あなたのペースで、あなたと愛犬らしく、ゆっくりと進んでいってください。
この連載が、その歩みの小さな灯火になれたら、本当にうれしく思います。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。



