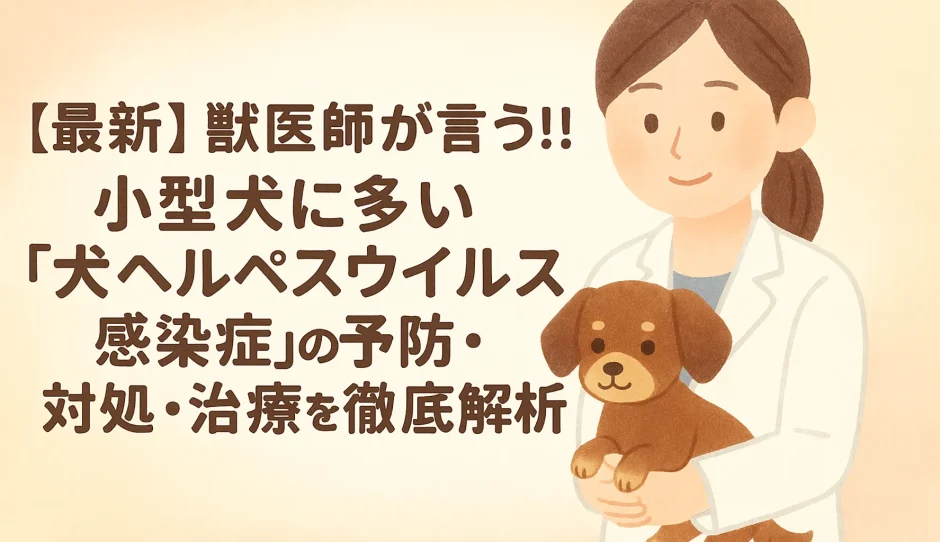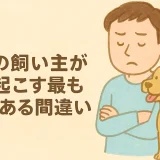犬ヘルペスウイルス感染症とは?その概要と小型犬への影響
犬ヘルペスウイルス(CHV)とは何か?
犬ヘルペスウイルス感染症(Canine Herpesvirus, CHV)は、主に犬科動物に感染するウイルス性疾患です。特に若齢犬や免疫力の弱い犬にとって深刻な影響を及ぼす可能性があります。このウイルスは、出生直後の子犬に致命的な影響を与えることがあるため、繁殖犬の管理においても注意が必要です。
CHVは主に、分娩時や産後すぐの母犬から子犬へ感染することが多く、空気感染や接触感染も報告されています。ウイルスの潜伏期間はおよそ6〜10日で、感染後すぐに症状が現れることもあれば、潜伏感染として体内に留まるケースもあります。
小型犬が特に感染しやすい理由
小型犬種は、体格が小さく代謝が速いため、免疫の発達が未熟な子犬期に感染すると症状が急速に進行しやすい傾向があります。また、ペットショップやブリーダーから迎えたばかりの環境変化もストレス要因となり、ウイルスへの抵抗力が低下しがちです。
さらに、小型犬は繁殖数も多いため、繁殖環境での衛生管理が不十分な場合、母犬から子犬への感染リスクが高まります。特にチワワ、トイプードル、ポメラニアンといった人気犬種での感染報告が目立つ傾向にあります。
一般的な感染経路と感染リスク
CHVは、唾液、鼻汁、膣分泌液などの体液を介して感染します。繁殖犬や集団飼育されている施設では、感染リスクが飛躍的に高くなります。以下のような状況では特に注意が必要です。
- 妊娠中の母犬が感染している
- 出産後の衛生管理が不十分
- 多頭飼育環境でウイルスが蔓延している
- ストレスや栄養不足で免疫力が低下している
このように、犬ヘルペスウイルス感染症は単なる風邪のような軽い疾患ではなく、特に小型犬の子犬においては命に関わる重大な疾患となり得ます。
犬ヘルペスウイルス感染症の主な症状とその見分け方

初期症状は非常に見逃されやすい
犬ヘルペスウイルス感染症(CHV)は、特に初期段階での症状が非常に軽微であるため、飼い主が気づかずに見逃してしまうケースが多々あります。子犬では急激に症状が進行しやすいため、早期の観察と対応が極めて重要です。
感染初期に見られる主な症状は以下のとおりです。
- 軽度の鼻水やくしゃみ
- 目やにや軽い結膜炎
- 元気がない、ぐったりしている
- 食欲不振
これらの症状だけでは、風邪や他のウイルス性疾患と区別がつきにくいため、CHVを疑うには飼育環境や感染経路を踏まえた総合的な判断が必要です。
重症化すると命に関わる症状も
特に生後2〜3週間以内の子犬が感染した場合、重篤な全身症状が現れやすく、死亡率も非常に高くなります。以下のような症状が見られる場合は、すぐに動物病院で診断を受けるべきです。
- 持続的な下痢や嘔吐
- 体温が極端に下がる(低体温)
- 呼吸が浅くなる、または苦しそうな呼吸
- けいれんや無反応といった神経症状
- 皮膚に赤い点状の出血(紫斑)
これらの症状が出る頃には、すでに全身にウイルスが広がっている可能性が高く、対処が遅れると致命的な結果を招く恐れがあります。
成犬でも無症状キャリアになることがある
成犬がCHVに感染した場合、多くは軽症または無症状で済みますが、ウイルスは体内に潜伏感染の形で残ることがあります。こうした犬は、ストレスや免疫低下時にウイルスを再活性化させ、他の犬への感染源となるリスクを持ち続けます。
特に、繁殖犬やブリーディング環境にいる犬は、無症状キャリアである可能性を念頭に置いた管理が重要です。
犬ヘルペスウイルス感染症の診断方法と検査の流れ
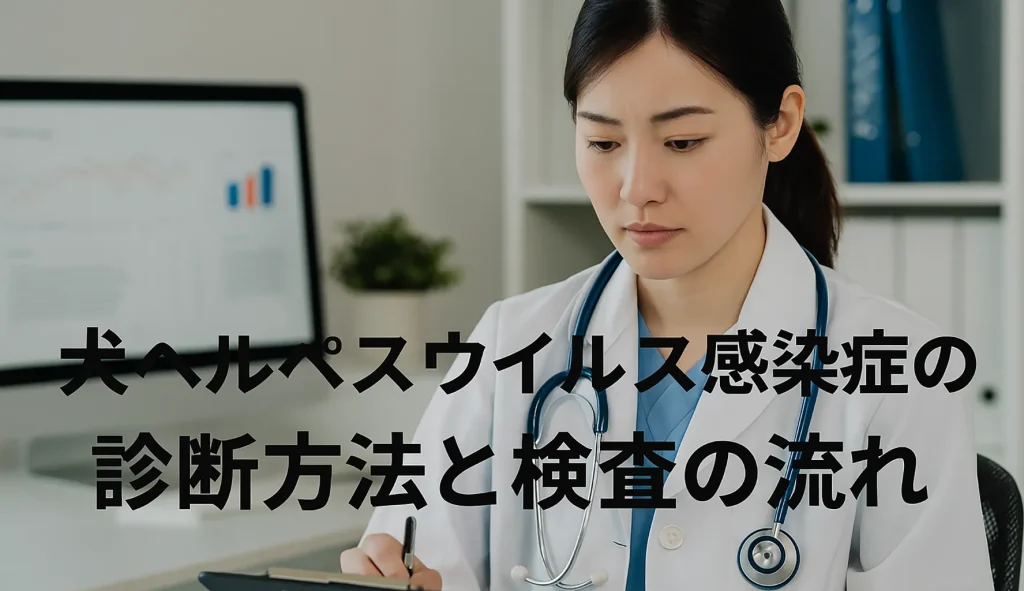
診断は総合的な判断が基本
犬ヘルペスウイルス感染症(CHV)の診断には、症状の確認だけでは不十分です。特に初期症状が風邪や他のウイルス疾患と似通っているため、獣医師による総合的な診断が不可欠です。
診断は以下の3つの要素を組み合わせて行われることが一般的です。
- 問診(既往歴・飼育環境)
- 身体検査(症状の確認)
- 各種検査(ウイルスの有無を確認)
実施される主な検査方法
CHVを特定するためには、いくつかの検査手法が用いられます。以下に代表的なものを紹介します。
1. PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応)
ウイルスの遺伝子を検出する方法で、最も精度の高い検査です。唾液、目やに、鼻汁、膣分泌液などの検体を採取して行います。感染初期でも陽性反応が出やすく、診断における信頼性が高いとされています。
2. 抗体検査(血液検査)
CHVに対する抗体の有無を確認する検査です。過去に感染していたか、ワクチンによる免疫があるかを判断できます。ただし、感染初期や子犬では抗体値が検出されないこともあります。
3. 病理組織検査(死後診断)
子犬が急死した場合などには、病理解剖によってCHVの感染を確認することがあります。組織からウイルスを検出し、感染経路や病態の進行を把握するのに有効です。
検査を受けるタイミングと留意点
感染が疑われる場合、症状が出た直後に検査を受けることが望ましいです。特に繁殖犬を所有している場合や、出産直後の子犬に異常が見られた場合は、早急な対応が求められます。
また、ウイルスは一定期間体内に潜伏する可能性があるため、一度陰性でも再検査が推奨されるケースもあります。獣医師と相談しながら、適切なタイミングで検査を実施しましょう。
犬ヘルペスウイルス感染症の治療法と対処手段

現時点では特効薬は存在しない
犬ヘルペスウイルス感染症(CHV)は、現段階でウイルス自体を完全に駆除する特効薬は存在していません。そのため、治療の基本方針は「対症療法」と「免疫力の維持」によるサポートが中心となります。
特に子犬の場合、発症後の進行が非常に速いため、早期の気づきと迅速な処置が生死を分けることになります。
子犬に対する治療法
生後2〜3週間の子犬が感染した場合、以下のような集中的なケアが必要です。
- 保温管理:低体温になりやすいため、適切な温度(30〜32度程度)に保つ。
- 点滴や栄養補助:自力で飲食が困難な場合は静脈点滴や流動食で補助する。
- 抗生物質の併用:ウイルスによる二次感染を防ぐ目的で投与されることがある。
- 免疫グロブリン投与:母犬からの抗体が不足している場合、免疫グロブリン製剤が使われることもある。
重篤な神経症状や臓器障害が出ている場合は、残念ながら治療が間に合わないことも少なくありません。
成犬の対処法とキャリア管理
成犬が感染しても、軽度な症状で済むことが多いため、安静と栄養管理で自然回復を待つケースが一般的です。ただし、ウイルスが体内に潜伏するキャリアとなる可能性があるため、以下のような注意が必要です。
- 妊娠犬の事前検査と管理
- ストレスを避ける生活環境の整備
- 他の犬への感染を防ぐ隔離措置
- 繁殖計画前に健康診断を徹底する
特に繁殖犬では、発情期や出産前後のストレスでウイルスが再活性化し、子犬に感染するリスクがあるため、獣医師との連携が不可欠です。
動物病院でのサポート体制
動物病院によっては、CHVへの対応実績や抗体測定、予防管理を専門的に行っているところもあります。感染が疑われる場合は、CHVに詳しい獣医師のもとで対応を受けることが推奨されます。
また、集団飼育を行っているブリーダーやペットショップは、感染拡大を防ぐためにも衛生管理の徹底と定期的な健康チェックを怠らないことが求められます。
犬ヘルペスウイルス感染症の予防法と感染拡大防止策
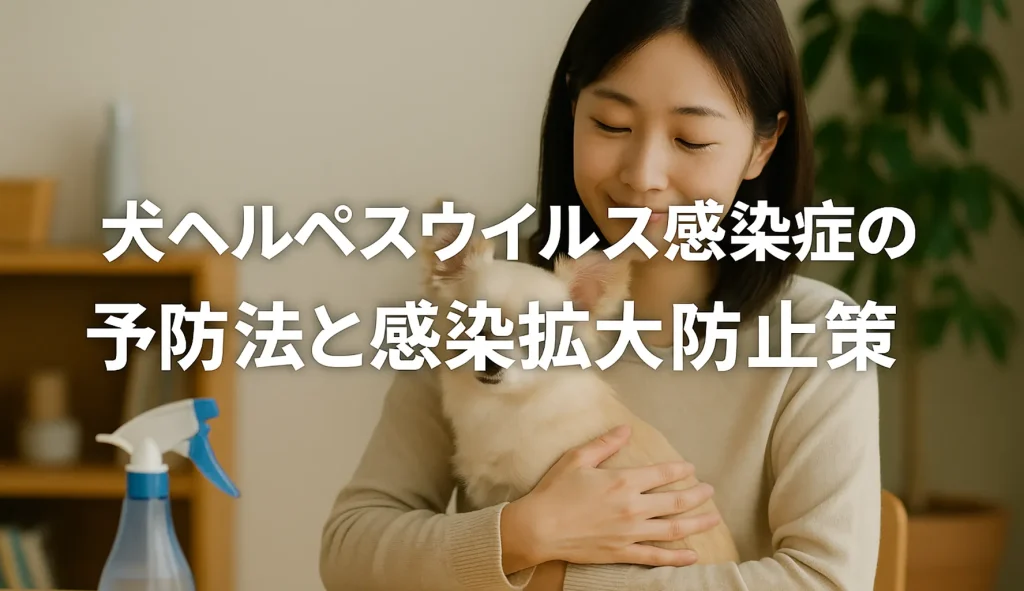
感染を防ぐための基本は「環境管理」と「衛生対策」
犬ヘルペスウイルス感染症(CHV)の感染予防において、最も重要なのは「日常的な衛生管理」と「ストレスの少ない飼育環境」です。CHVは体液や飛沫を介して感染するため、ウイルスが繁殖しにくい清潔な空間を維持することが、予防の第一歩となります。
具体的な対策として、以下の点が挙げられます。
- 定期的なケージや寝床の消毒(次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を使用)
- 飼育スペースの換気を十分に行う
- 食器や給水器をこまめに洗浄・消毒する
- 他犬との不要な接触を避ける(特に発情期・出産前後)
妊娠犬・繁殖犬の管理は特に重要
CHVは母犬から胎児または出生直後の子犬に感染することが多く、繁殖に関わる犬は特に厳密な感染対策が必要です。
- 繁殖前に抗体検査を行い、感染の有無を確認する
- 妊娠中の犬をストレスの少ない静かな環境で飼育する
- 分娩室は無菌に近い状態に保ち、出産直前から隔離する
- 他の犬との接触を極力避ける
また、出産後の母犬は一時的にウイルスを再活性化させるリスクがあるため、子犬の感染を防ぐ目的で人工保育を検討するケースもあります。
ワクチンは存在するのか?
CHVに対するワクチンは、日本国内では一般的に流通しておらず、定期接種ワクチンプログラムにも含まれていません。ただし、一部の繁殖施設では、特別な事情に応じて免疫グロブリンの投与や海外製のワクチンを用いた感染対策が実施されているケースもあります。
ワクチンの導入可否については、獣医師との相談が必要です。特に繁殖犬の健康管理を重視するブリーダーは、ワクチンの有無にかかわらず、常に感染リスクを意識した行動が求められます。
多頭飼育時の感染拡大防止策
1頭の犬がCHVに感染していることが判明した場合、同居犬や接触のあった犬への感染防止策が急務です。
- 感染犬を別の部屋に隔離し、専用のケージや食器を使用する
- 飼い主が複数の犬を世話する際は、必ず手指と衣服の消毒を徹底する
- 獣医師の指導のもと、健康状態の観察を続け、必要に応じて検査を受けさせる
集団飼育やペットホテル、ドッグラン利用者も、感染リスクを考慮したうえで行動することが推奨されます。
感染を未然に防ぐ!飼い主ができる日常ケアと注意点

日々の観察と早期発見が感染予防の鍵
犬ヘルペスウイルス感染症(CHV)のような潜伏感染型のウイルスに対しては、飼い主による日常的な観察と適切な健康管理が、感染の予防と早期対処に直結します。特に子犬や高齢犬、小型犬など免疫力が不安定な個体を飼育している場合は、次のようなポイントを日常的にチェックしましょう。
- 食欲や元気の有無
- 呼吸の状態(速さ・浅さ)
- 鼻水、目やにの量と色
- 排泄のリズムと状態(下痢・便秘の有無)
- 突然の体温変化やけいれんなどの異常行動
これらの変化が見られた場合は、早めに動物病院で診察を受けることが重要です。
ストレスを最小限にする環境づくり
CHVは、ストレスによって再活性化する性質があります。そのため、飼い犬の生活環境はできる限りストレスの少ないものに整えることが予防につながります。
具体的な環境管理のポイントは以下のとおりです。
- 静かで落ち着いた生活空間を確保する
- 適度な運動と十分な休息をバランス良く取り入れる
- 急激な温度変化や騒音を避ける
- 家族構成の変化や留守番時間の急増などに配慮する
特に出産前後や引っ越し・旅行などの生活変化時には、免疫力が一時的に低下しやすいため注意が必要です。
繁殖を予定している飼い主へのアドバイス
繁殖犬の飼い主は、一般的な家庭犬以上にCHV感染リスクを把握し、事前の準備と健康管理を徹底する必要があります。
- 繁殖前に抗体検査を受ける
- 感染リスクのある犬との接触を避ける
- 妊娠後の母犬は隔離と静養に努める
- 子犬が誕生した場合は、一定期間の観察を強化する
感染防止と健康な子犬の誕生のためには、専門の獣医師と密に連携し、事前に予防計画を立てることが重要です。
まとめ:飼い主の意識が感染症リスクを大きく左右する
犬ヘルペスウイルス感染症は、軽視できないウイルス疾患です。特に小型犬や子犬にとっては、命に関わる重大なリスクをはらんでいます。しかし、正しい知識と日常的なケア、早期の異常察知ができれば、予防や感染拡大の防止は十分に可能です。
「うちの子は大丈夫」と過信せず、常に犬の様子を観察し、必要であれば獣医師に相談する習慣を持つことが、愛犬の健康を守る最大の防御策です。
筆者の想い
犬を家族として迎えるということは、その命と向き合い、守り続ける責任を持つということです。特に小型犬は、体の小ささゆえにちょっとした病気が大きな問題へとつながることがあります。犬ヘルペスウイルス感染症もそのひとつで、見過ごされがちな感染症でありながら、子犬にとっては命を脅かすほど深刻なものです。
この記事を通じて、飼い主の皆さんがこの病気に関する正しい知識を持ち、日々のケアや予防策に意識を向けていただけたらと願っています。何より大切なのは、「うちの子に限って」は通用しないという意識です。愛犬の健康を守ることができるのは、他でもない飼い主自身なのです。
私たちができる小さな注意や行動が、愛犬の未来を守る大きな力になります。この情報が、一頭でも多くの犬の命と健康を守る一助となれば幸いです。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。