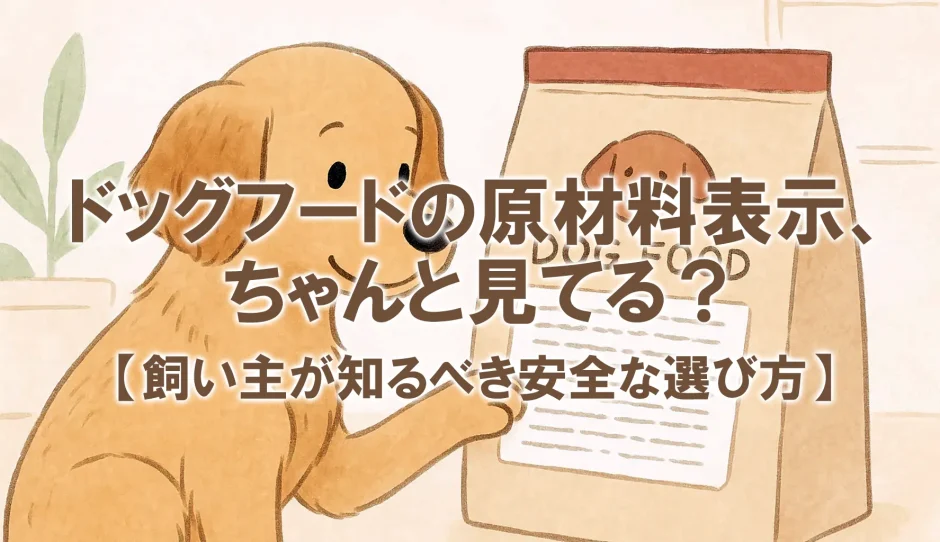原材料表示を読む力が、愛犬の健康を左右する
ドッグフードのパッケージ裏にずらりと並ぶ原材料表示。正直なところ、「なんとなく見てはいるけど、よく分からない」という方が多いのではないでしょうか。けれど、私はここを読み解けるようになることが、飼い主としての大切な責任だと考えています。
実際、フードのパッケージに「チキン」と書かれていても、それが新鮮な生肉なのか、加熱処理されたチキンミールなのか、副産物を含むものなのかで、栄養価や安全性は大きく変わります。表面のキャッチコピーやイメージに惑わされず、細部まで目を通す力が求められます。
また、私自身、かつては「グレインフリー」や「無添加」という言葉に安心してしまい、内容を深く確認しないまま購入していたことがありました。しかし、そういった表示があっても、実際には消化に負担をかける素材や、アレルゲンとなりうる添加物が入っている場合も少なくありません。
愛犬の体は、日々の食事からつくられていきます。だからこそ、「どんな成分が含まれているのか」だけでなく、「何が使われていないのか」も見極めることが大切です。これは、ペットフードに限らず人間の食事と同じ感覚だと私は思います。
次章では、原材料表示の中で特に注目すべきポイントや、見落としがちなチェック項目について、より具体的に解説していきます。初心者の方でもすぐに実践できる内容にまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
原材料表示で注目すべき3つの視点――私が必ずチェックしているポイントとは

ドッグフードを選ぶとき、原材料表示に目を通すのは「健康に気をつかっている飼い主」としては当然のことです。ただ、いざ表示を見ても専門用語が並んでいて「どこを見れば良いのかわからない」と戸惑う方も多いはず。私自身も、以前はそのひとりでした。
でも、何度も試行錯誤するうちに、信頼できるドッグフードを選ぶためには“最低限ここは押さえるべき”というポイントが見えてきました。今回は、私が原材料表示をチェックする際に必ず確認している3つの視点を紹介します。
1. 一番最初に書かれている原材料は何か?
原材料表示は、含有量の多い順に記載されています。つまり、最初に書かれている食材が、フードの主成分です。ここが「チキン」や「サーモン」など、具体的な動物の名前で明記されていれば、比較的安心できると私は考えています。
逆に「肉類」「動物性油脂」といった曖昧な表現が使われている場合、どの動物由来か分からないことが多く、私としては避けたいところです。食の透明性が求められる時代に、“中身が分からない”というのは、愛犬の健康を預けるにはあまりにリスクが大きいと感じます。
2. 添加物・保存料に目を光らせる
次に気をつけたいのが、添加物や保存料の種類。中には安価なフードに、酸化防止のための合成添加物(たとえばBHAやBHTなど)が使われているケースもあります。
個人的に私は、なるべく天然成分で保存されているフードを選ぶようにしています。たとえばビタミンE(トコフェロール)やローズマリー抽出物などは、安心して与えられる素材だと感じています。ただし、無添加をうたうフードにも、保存性の面で課題がある場合があるので、そのあたりのバランスは要チェックです。
3. 穀物の有無より“扱われ方”を見極める
最近は「グレインフリー(穀物不使用)」が人気ですが、私は一概に“穀物=悪”とは思っていません。ポイントは、どんな穀物が、どのような意図で使われているか。
たとえば、犬にとって消化しにくい小麦やトウモロコシがメインに使われている場合、それはコストを抑えるための“かさ増し”目的かもしれません。こうしたケースは、正直、あまり好感が持てません。
一方で、オートミールや玄米のように、比較的消化吸収に優れ、栄養価も高い穀物であれば、私はむしろ歓迎すべき素材だと考えています。大事なのは「入っているかどうか」ではなく「どう使われているか」なのです。
この3つの視点は、飼い主として私がドッグフードを選ぶ上での「基準点」になっています。完璧なフードは存在しないかもしれませんが、せめて中身を見極められる目だけは持っていたい。その積み重ねが、愛犬の健康を守る最初の一歩になると私は信じています。
次章では、原材料表示でよく見かける「曖昧な表現」や、見逃しやすい要注意ワードについて詳しく解説していきます。
その表現、本当に安心?“曖昧ワード”の見抜き方

ドッグフードの原材料表示を読み解くうえで、私がいつも警戒しているのが“曖昧な言い回し”です。一見よさそうに見える表現でも、内容が不明確なまま使われていることが少なくありません。
正直に言うと、私もかつては「ナチュラル」や「プレミアム」という言葉に惹かれて、パッケージの雰囲気だけで選んでしまったことがあります。けれど、それでは中身の本質を見落としてしまう。そう気づいてからは、言葉の裏にある“意図”を読み取るようになりました。以下に、私が注意して見ている3つの“曖昧ワード”を解説します。
1. 「〇〇ミール」や「副産物」など、正体があやふやな原料名
たとえば「チキンミール」や「家禽副産物粉」といった表記。一見、栄養価の高そうな素材に見えますが、何が含まれているのかはかなり幅広い可能性があります。部位の明記がなければ、骨、皮、臓器、時にはくちばしや羽が使われている可能性もゼロではありません。
私としては、ミールという言葉自体を悪者にするつもりはありません。実際、良質な乾燥肉を使っているメーカーもあります。ただ、それがどんな原料由来なのかが明確に示されていない場合、そのフードに安心感は持てません。大切なのは「何が使われているか」ではなく、「何が明確に示されているか」だと私は考えています。
2. 「ナチュラル」「自然由来」など、響きだけが先行する言葉
「ナチュラル」「自然派」と聞くと、身体に良さそうな印象を受けますよね。私も以前はそうでした。でも、実際に原材料表示を見てみると、「ナチュラルフレーバー」や「植物由来抽出物」といった、何となく良さそうに聞こえるだけの成分名が目につくことがあります。
問題なのは、その“ナチュラル”が具体的に何から来ているのかが、ほとんどの場合書かれていないこと。経験上、このようなふわっとした言葉の裏には、消費者の安心感を利用しようとする意図を感じることがあります。私は、明確な説明がないままイメージだけで売られている商品には慎重な姿勢を崩さないようにしています。
3. 「総合栄養食」「基準クリア」の過信に注意
「総合栄養食」や「AAFCO基準を満たしています」といった文言も、つい安心材料にしたくなります。でも、私の感覚では、これらは“最低限の栄養バランスを整えている”という程度の証明であって、高品質であることを保証するものではありません。
あくまでこれは「基準点をクリアした」というだけ。私はこの手の表示を“入り口”として見るようにしていて、あとは実際の原材料の質や透明性で判断します。言ってしまえば、合格ラインは越えていても、優秀かどうかは別問題なのです。
こうした曖昧な表現に振り回されないためには、言葉の裏側にある「意図」を読み解く視点が欠かせません。原材料表示は、ただの一覧表ではなく、メーカーがどこまで“ごまかさずに伝えているか”を見極めるツールでもあるのだと、私は実感しています。
次章では、実際に私が「これは避けたい」と判断している原材料について、なぜそう思うのかを理由とともにご紹介します。
私が選ばないと決めた原材料――その判断基準とは

ドッグフードの原材料表示を丁寧に読み解くようになってから、私はある種の「選ばない基準」も明確になってきました。もちろん、犬によって合う合わないはありますし、すべてのフードが悪いとは言いません。ただ、私自身の体験や愛犬の反応を通して、「これだけは避けている」と断言できる原材料があります。
ここでは、私がなぜそれらを避けるようになったのか、その理由を具体的にお伝えします。
1. 曖昧すぎる「副産物」や「エキス」類
「○○副産物」や「○○エキス」といった表記は、ドッグフードによく登場します。かつての私は、その意味を深く考えずに「何となく風味付けなのかな」と軽く受け止めていました。
でも調べてみると、それらは明確な部位が特定されていない原料であることが多く、たとえば副産物には内臓、骨、皮、時にはどの部位かすら不明なものが混ざっている可能性もあります。正直、それを大切な家族である愛犬に与えるのは抵抗があります。
私は、「チキン」や「サーモン」といった具体的な食材名が書かれているものを信頼するようにしています。やはり“何を使っているのか明確に書けないフード”には、疑いを持ってしまいます。
2. 合成酸化防止剤(BHA・BHT・エトキシキン)は選ばない
フードの保存性を高めるために使用される合成酸化防止剤。「ごく微量だから問題ない」という意見もありますが、私はその考え方にはあまり共感できません。たとえ基準値内であっても、日々の積み重ねが体に影響を与えないとは限らないと感じるからです。
実際、うちの愛犬は、これらの成分が入っているフードを与えていた頃、毛並みにツヤがなくなり、口元に湿疹のようなものが出始めました。フードを切り替えてからそれがピタッと収まったのを見て、「やっぱり関係があるのかも」と思ったのが、私が合成添加物を避けるようになったきっかけです。
今は、ビタミンEやローズマリー抽出物など、天然の保存料が使われているかどうかを基準にしています。完全無添加が理想とはいえ、現実的には“何で保存されているか”が重要な視点だと思っています。
3. トウモロコシ・小麦・大豆が“主原料”のフードには慎重に
穀物類が入っているからといって、即NGとは思っていません。ですが、原材料の上位に「トウモロコシ」「小麦」「大豆」が並んでいるフードは、私の中で“要注意”という位置づけです。
理由は2つ。ひとつは、消化が難しいケースがあること。もうひとつは、それらが動物性たんぱく質の代わりに「かさ増し」として使われていることがある点です。栄養というより“量を確保するため”という印象を受けるのです。
うちの子も、以前小麦ベースのフードを与えていたとき、かゆみや皮膚トラブルに悩まされました。切り替えたらピタリとおさまったこともあり、それ以来、私は主原料に動物性たんぱく質がしっかりと書かれているフードを選ぶようになりました。
原材料を見極める力は、一朝一夕で身につくものではありません。でも、繰り返しフードを選び、愛犬の体調を観察していくなかで、少しずつ“自分なりの基準”ができてくるはずです。私の場合、それが今回ご紹介した3つの視点でした。
次章では、「では実際にどんな視点でフードを選べばいいのか?」という疑問にお答えすべく、信頼できるドッグフードを選ぶためのチェックポイントをまとめてご紹介します。
信頼できるドッグフードを見極める5つの視点

ここまで、原材料表示の読み方や避けたい成分についてお話ししてきました。でも実際にお店や通販サイトでフードを選ぶ場面になると、「どれがいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。私自身も、最初は毎回選ぶたびに迷っていました。
しかし今では、「ここを押さえれば、失敗は少ない」と思えるチェックポイントがはっきりしてきました。今回は、私が実際にドッグフードを選ぶ際に重視している5つの視点をご紹介します。
1. 主原料に“動物性たんぱく質”が明記されているか
フードの主成分が何かは、まず一番最初にチェックすべき項目です。原材料の1番目に「チキン(生肉)」「ラム肉」などの具体的な動物性たんぱく質が記載されているかどうか。これは私のなかで絶対に外せないポイントです。
逆に、「動物性原料」や「肉類」といった、ぼかした表現になっているものは避けるようにしています。曖昧な表示には、どうしても不信感が残るからです。
2. 製造元・原産国の情報が開示されているか
原材料と同じくらい大事なのが「どこで作られているか」という情報です。私の経験では、信頼できるフードメーカーは原産国や製造工場の衛生管理状況などをきちんと開示しています。
個人的には、「国内製造」であっても中身の原料が輸入品であれば、その出どころもチェックするようにしています。表示に“誠実さ”を感じられるメーカーは、それだけで信頼に値すると思っています。
3. 不要な添加物が使われていないか
保存料、着色料、香料など、余計な添加物がずらりと並んでいないかどうかは、必ず確認しています。とくに「○○色素」「香料」といった、人間向け商品で見慣れた成分があるときは注意。
私は、見た目や香りを良くすることよりも、犬にとっての安全性や自然な風味を重視したいと思っています。あくまで“犬の健康を最優先する姿勢”が見えるフードに安心感を覚えます。
4. 栄養バランスが明記されているか
「総合栄養食」と書かれているからOK…ではなく、実際の栄養バランスまで目を通すようにしています。たんぱく質や脂質の割合、カロリー、オメガ3・6脂肪酸の有無など、細かく見ていくと、そのフードの“本気度”が分かってきます。
私が選ぶ基準としては、たんぱく質は25%前後以上、脂質も10〜15%程度あるものが理想です。もちろん犬の年齢や体調にもよりますが、少なくとも“どんな栄養で体を支えているのか”を見ずに選ぶことは、今では考えられません。
5. 実際のレビューや愛犬の反応も参考に
最後に大切なのは、やはり「実際に与えてみたときの反応」です。口コミも参考にはしますが、最終的には自分の犬がどう感じるか、どう変化するかを見るのが一番正直な評価だと思っています。
うちの子は、あるフードに切り替えてから便の状態が安定し、毛並みにツヤが出たことで、「これだ」と確信できました。与える前と後の違いを冷静に観察することが、フード選びの精度を高めるコツだと感じています。
ドッグフードは、パッケージの派手さや人気ランキングだけでは見抜けない“中身の質”があります。だからこそ、自分の目で情報を読み取り、納得して選ぶことが、愛犬の健康を守る上でとても大切だと私は思います。
次章では、この記事のまとめとして、私がなぜここまで原材料にこだわるようになったのか、そしてその背景にある想いについてお話しします。
原材料表示にこだわる理由――私が大切にしている想い

ここまでお読みいただきありがとうございます。最後に、この記事全体を通して私が伝えたかったこと、そしてなぜこれほどまでに“原材料表示”にこだわるようになったのか、その理由をお話しさせてください。
正直なところ、以前の私は「愛犬にはいいものを食べさせたい」と言いつつ、どこかで“パッケージが可愛いから”とか“評判が良いらしいから”という理由でフードを選んでいました。でも、ある時ふと気づいたんです。犬は自分で食事を選べない。選ぶのはいつだって、私たち飼い主なのだと。
それからというもの、私は“見るべきものをちゃんと見る”ようになりました。中身の質、添加物の有無、製造元の姿勢…細かい部分までしっかり確認するようになってから、愛犬の体調も明らかに変わってきました。
もちろん、完璧なドッグフードなど存在しないかもしれません。ですが、「何が良くて、何が不安要素なのか」を自分の目で判断できるようになれば、少なくとも“なんとなく不安”な気持ちを抱えたままフードを与えることはなくなります。
私にとって原材料表示とは、単なる成分一覧ではありません。それはメーカーがどこまで誠実にフードづくりをしているかを示す「信頼の証」でもあり、そして何より、“愛犬に責任を持って向き合うための判断材料”だと考えています。
ドッグフード選びに正解はありません。でも、愛犬のために真剣に選ぼうとする気持ちは、必ず犬にも伝わると私は信じています。この記事が、あなたと愛犬の健やかな毎日のヒントになれば、こんなにうれしいことはありません。
まとめ:ドッグフードの原材料表示を見ることは、愛犬への思いやりの形のひとつです。迷ったときは、「何を与えるか」ではなく、「なぜそれを選ぶのか」に立ち返ってみてください。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。