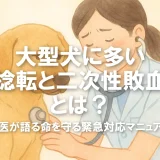なぜ大型犬に多い?「MRSP感染」のリアルな脅威
多剤耐性ブドウ球菌――MRSP(Methicillin-Resistant Staphylococcus pseudintermedius)という名前にピンとこない飼い主さんも多いかもしれません。ですが、これは今、動物病院の現場で確実に増えてきている厄介な感染症です。私自身、ここ数年でMRSPの診断数が明らかに増えているのを肌で感じています。特に、大型犬の皮膚疾患や術後の傷の悪化を追っていくと、この菌が見つかるケースが目立ちます。
MRSPがやっかいなのは、一部の抗生物質がまったく効かないこと。以前なら「とりあえずこの薬で様子を見よう」と選んでいた抗菌剤が通用しない場面が増え、治療の選択肢が限られてしまうことがあります。しかも、一度治ったように見えても、数週間後にはまた同じ部位が腫れてきたり、膿が溜まったりする――そんな再発例も少なくありません。
なぜ大型犬に多いのか?と問われれば、いくつかの傾向が見えてきます。私の実感としては以下のような要因が関係していると感じています。
- 体が大きいぶん、散歩や遊びで小さな傷を負いやすい
- 皮膚のしわや耳の中に湿気がこもりやすく、菌が繁殖しやすい環境ができやすい
- ドッグランや多頭飼いなど、他犬との接触頻度が高いことで菌が広まりやすい
- 過去に長期的な抗菌薬治療を受けていた既往歴があることも
MRSPは、感染そのものも厄介ですが、それ以上に「どう治すか」より「どう防ぐか」が重要になってくると私は思っています。適切な衛生管理はもちろんですが、飼い主自身が“愛犬の皮膚トラブルに早く気づく目”を持つことが、何よりの予防策です。
次章では、MRSPがどのように感染するのか、どんなサインを見逃さずにいれば早期発見につながるのかを、より具体的に解説していきます。
見落としがちな感染ルートと、MRSPの“最初のサイン”とは

MRSP(多剤耐性ブドウ球菌)は、一見すると日常の延長線上に潜んでいる病原菌です。私自身、診察の中で「まさかそんなところから?」と驚かされたケースも少なくありません。これは特別な病気ではなく、“いつもの生活習慣”の中に入り込んでくる可能性があることを、まず知っておいていただきたいのです。
感染源は案外そばにある
MRSPは、皮膚のわずかな傷や、粘膜などの目に見えにくい部位から侵入します。たとえば、散歩中に草むらで枝にこすれた、ドッグランで他の犬とじゃれ合った、そんな日常の一場面が感染のきっかけになることもあります。
私が現場でよく感じるのは、以下のような状況が重なると、感染のリスクが一気に高まるということです。
- 耳の奥や肉球の間など、湿気がこもる場所のケアが甘い
- アトピー性皮膚炎などで皮膚バリアが弱っている
- 抗生物質を頻繁に、または長期的に使用している
- 多頭飼いや外出頻度が多く、他犬との接触機会が多い
これらは一つひとつは些細に思えるかもしれませんが、私の印象としては「小さな無自覚」が積み重なって、感染につながっているケースが非常に多いです。
“軽い皮膚炎”と見分けがつかない初期症状
MRSPに感染した初期段階では、はっきりとした違いが見えにくいという難しさがあります。実際に多くの飼い主さんが「ただの湿疹かと思った」「前に処方された塗り薬で治ると思った」と言います。しかし、それらが効かずに症状が長引くのが、この菌の特徴でもあります。
私が診療で注意している“気になるサイン”は、たとえば以下のようなものです。
- 治療をしてもかゆみや赤みがなかなか改善しない
- 一度良くなったと思った箇所が、しばらくしてまた悪化する
- 傷口からの膿が濁った黄色や緑色で、においが強い
- 外耳炎が繰り返し発生し、毎回同じような抗生物質では効果が薄い
こうした症状が出ている場合、表面的な皮膚炎ではなく、何か“根の深い感染症”が潜んでいる可能性を疑ったほうがいいと私は考えています。
初期の段階で「これはおかしい」と気づけるかどうかは、愛犬の普段の様子をしっかり観察しているかにかかっています。だからこそ、飼い主さんの“ちょっとした違和感”を大切にしてほしいと強く思います。
次章では、万が一MRSPに感染してしまった場合に、どのような治療やケアの選択肢があるのかについて掘り下げていきます。現場で実感している「治療の難しさ」と「希望の持ち方」を、できるだけ具体的にお伝えします。
MRSP感染が判明したら?治療の現実と“付き合い方”の選択

MRSP(多剤耐性ブドウ球菌)の診断が下ると、多くの飼い主さんが驚き、そして不安を抱きます。それも当然です。「耐性菌」と聞くだけで、治らないのでは?薬が効かないのでは?と感じる方も多いでしょう。
ただ、私がこれまで多数のMRSP症例を診てきた中で強く思うのは、「慌てず、あきらめず、長期的視点で向き合うこと」が何より大切だということです。MRSPは確かに簡単には治りませんが、“管理していける感染症”でもあります。
抗菌薬だけに頼らないという選択肢
MRSPは多くの抗菌薬に対して耐性を持っているため、従来のように「症状が出たら抗生物質」というスタンスでは立ち行かないことがあります。私が臨床で意識しているのは、抗菌薬“だけ”に依存しない治療方針を組み立てること。
たとえば:
- 細菌培養と感受性試験を行い、使える薬を絞り込む
- スキンケアの見直し(保湿や洗浄剤の選定)
- 免疫力の底上げを目的とした食事やサプリメントの提案
- 局所療法や漢方などの代替療法の併用
これらは決して特別なことではなく、MRSPに限らず“慢性疾患”と向き合うときの基本でもあります。
「完治」よりも「共存」への意識転換
MRSP感染をした皮膚炎などは、時に数カ月~年単位のケアが必要になることもあります。飼い主さんには「すぐに完治を目指す」というよりも、「悪化を防ぎながら、愛犬が快適に過ごせる状態をキープする」ことに焦点を当てていただくよう、日々お話ししています。
実際、MRSPに感染した犬でも、きちんと管理を続けることで、日常生活に大きな支障なく過ごせている子たちはたくさんいます。
「この子とどう付き合っていくか」という視点が持てるようになった瞬間、飼い主さんの表情がふっと軽くなるのを何度も見てきました。それが、私にとってこの病気と向き合ううえでの一番の希望でもあります。
次章では、MRSP感染を未然に防ぐために、日々のケアや環境管理で何ができるのか――“予防”にフォーカスした具体策をご紹介していきます。
MRSPを寄せつけない!大型犬に本当に必要な日常ケアと予防の視点

MRSP(多剤耐性ブドウ球菌)は、一度感染すると治療が長引きやすく、生活の質そのものに影響を与える菌です。だからこそ、私が臨床の現場で何より大切にしているのが「予防」という考え方。特に大型犬は、構造的にも環境的にも感染リスクが高まりやすいため、日々の習慣をほんの少し見直すだけで、防げるケースも意外と多いのです。
湿気対策は“丁寧さ”がカギ
大型犬は耳が垂れていたり、皮膚に厚みがある分、蒸れやすい構造をしています。人間でいうならば、毎日靴を履きっぱなしのようなもの。ちょっとした湿気の蓄積が、皮膚トラブルの温床になってしまうのです。
私の経験では、以下のようなケアを“雑にしない”ことが、最もシンプルで確実な予防になります。
- 散歩やシャンプーの後は、タオルドライ+ドライヤーでしっかり乾かす
- 耳の中や指の間は、目視して湿っていないか確認する習慣をつける
- 湿疹が出やすい部位には、保湿剤で皮膚バリアを強化する
この「毎日の当たり前」を丁寧に続けるかどうかが、数か月後の差になります。
抗菌シャンプーの“誤解”に注意
感染症が怖いあまり、市販の薬用シャンプーを過剰に使ってしまう方もいますが、それはかえって皮膚を痛めることも。私の感覚では、薬用シャンプーは“処置”であって“予防”ではありません。常在菌まで洗い流してしまうリスクを考えると、皮膚にやさしい中性タイプや保湿成分入りのシャンプーをメインにするほうが、長い目で見て安心です。
他犬との接触後は“ひと手間の習慣”を
ドッグランやサロンで他犬と接触したあとは、蒸しタオルで体を拭いてあげるだけでも、表面の菌をかなり減らすことができます。私の犬にも実践しているのは、耳・首まわり・肉球の間を中心に「軽く拭いてリセットする」こと。特別な消毒液を使わなくても、皮膚の状態を崩さずにケアできるのでおすすめです。
感染予防は“心身の健康づくり”から
感染症は、菌そのものの強さよりも、「かかりやすい状態」があるかどうかの方が重要です。実際、同じ環境にいても、ストレスの多い犬や栄養状態が不安定な犬ほど症状が出やすい印象があります。
私は、栄養バランスの整った食事、適度な運動、そして何より“家の中で安心できる空間”が、最大の予防策だと思っています。皮膚のバリア機能は、心の安定とも深くつながっています。
感染を完全に防ぐことは難しくても、“かかりにくい体”をつくることはできます。そのためにできる日々のケアこそ、飼い主が愛犬のためにできる最良の行動ではないでしょうか。
次章では、MRSPが他の動物や人間にうつる可能性について、そして多頭飼い家庭で気をつけるべき点を詳しく解説していきます。
MRSPはうつるのか?人や他のペットへの感染リスクと多頭飼いの心得

MRSP(多剤耐性ブドウ球菌)という名前が診断書に載った途端、「他の子にもうつるのでは?」「人間にも感染する?」という不安を抱える飼い主さんは少なくありません。私も実際、診察室でそうした質問を何度も受けてきました。
結論から言えば、過度に怖がる必要はありません。ただし、“正しく理解し、無理のない範囲で気をつける”という姿勢は必要だと私は思っています。
人への感染リスクは極めて低いが、配慮は必要
まず、MRSPは人間にもうつるかという点について。現時点では、健康な成人がペットからMRSPに感染する例はごく稀であり、実際私自身もこれまでの診療で体調を崩したことはありません。
ただし、すべての人が安心というわけではありません。高齢者や乳児、重度の基礎疾患を持つ方など、免疫力が落ちている方が同居している場合は、念のため接触後の手洗いなど基本的な衛生対策はしておいたほうがいいでしょう。
私の感覚では、感染よりも“菌を家に持ち込まない・広げない”という意識のほうが現実的です。
多頭飼いで気をつけたい“接触”のポイント
多頭飼育の場合、MRSPを他の犬や猫にうつしてしまうリスクはゼロではありません。特に皮膚炎がある犬が、他の子と同じベッドで寝ていたり、舐め合ったりしていると、物理的に菌が移動する可能性があります。
私が診察の際に伝えている実践的な対策は以下のとおりです。
- 寝具やタオルは共有せず、個別管理にする
- 水やフードの容器は使いまわさず、それぞれ分けて使う
- 皮膚トラブルのある子にはエリザベスカラーや洋服を着せて舐め合いを防ぐ
- お手入れの順番は“健康な子→患犬”の順にし、道具はその都度洗浄する
これらは決して過剰な管理ではなく、“できる範囲で感染経路を断つ”ための工夫です。実際、多頭飼いでも感染拡大を防げている家庭は、こうしたちょっとした対策を徹底しています。
飼い主自身が“媒介者”にならないために
意外と見落とされがちなのが、飼い主の手や服を介した“間接感染”のリスクです。私自身も、診察でMRSP感染のある犬に触れたあとは、次の患者を診る前にしっかり手を洗い、白衣も一度脱ぎます。これは少し神経質すぎるように思えるかもしれませんが、実際こうした意識が感染予防の第一歩だと感じています。
家庭でも、感染犬の患部に触れたあとは手を洗う、膿が付着したガーゼやタオルは他の洗濯物と分ける、など基本的な衛生管理を心がければ、ほとんどのリスクは回避できます。
「清潔すぎず、でも油断せず」
MRSPは確かに厄介な菌ではありますが、「正しく恐れて、過剰に反応しない」ことが大事だと思っています。飼い主が神経質になりすぎると、犬自身がその空気を敏感に感じ取り、不安になってしまうこともあります。
“うつるかもしれない”という漠然とした恐れよりも、“どう防げばいいか”に意識を向けてあげてください。多頭飼いでも、適切に対応すれば、他の犬や家族が元気に過ごせているケースはたくさんあります。必要なのは、極端な消毒生活ではなく、「小さな配慮の積み重ね」だと私は考えています。
次章では、この記事の締めくくりとして、MRSPと向き合うなかで感じたこと、そして伝えたい想いを、筆者として率直に綴ります。
MRSPと向き合う中で見えてきたもの ――筆者として伝えたいこと

MRSP(多剤耐性ブドウ球菌)という言葉を聞いたとき、多くの飼い主さんが抱くのは「うちの子は大丈夫なんだろうか」「一生治らないのではないか」という不安です。その気持ちは、私にもよくわかります。実際、私も獣医師として初めてMRSPの診断を下したとき、正直に言えば、治療の難しさと向き合う覚悟が必要だと感じました。
ですが、これまで多くの感染症例に立ち会い、飼い主さんと二人三脚でケアを続けてきた経験から言えるのは、「MRSP=絶望」ではないということです。むしろ、それまでの飼育習慣や生活環境を見直すきっかけになり、結果的に犬との絆が深まったご家庭もたくさん見てきました。
“治すこと”だけがゴールではない
確かに、MRSPは完治が難しいこともあります。ですが、皮膚症状をうまくコントロールし、犬が快適に日々を送れていれば、それも立派な「治療の成果」だと私は考えています。
病気に対して必要以上に戦おうとするよりも、“その子らしく生きるために何ができるか”という視点で日々を整えていくことが、最終的には大きな安心につながります。これは私自身、何度も現場で感じたことです。
飼い主の“気づき”がすべての出発点
MRSPに限らず、犬の病気は“異変に早く気づけるか”が鍵です。ほんの小さな湿疹や、繰り返すかゆみ、耳のにおいなど、「なんとなくおかしいかも?」と思ったら、ためらわず相談してみてください。
その“なんとなく”を大切にできる飼い主さんほど、愛犬を守る力があると私は思っています。逆に、「前もこうだったし大丈夫」「様子見でいいかな」といった判断が、状態を長引かせる原因になることもあるのです。
“完璧じゃなくていい”からこそ、続けられるケアを
私は、治療も予防も“無理なく続けられること”が一番だと感じています。難しい専門知識よりも、毎日体を拭いてあげる、寝具を清潔に保つ、食事の質を少し見直す――そんなシンプルなことの積み重ねが、結果として大きな予防力になります。
MRSPは、確かに軽く見てはいけない感染症ですが、同時に「共に暮らしていくための知恵」を与えてくれる存在でもあります。
最後に ――犬の健康は“家族の在り方”の映し鏡
この記事を通して伝えたかったのは、MRSPの知識だけではありません。犬の病気とどう向き合うか、家庭という単位でどう支えるか――そうした“飼い主としての姿勢”そのものです。
私は、病気と闘うというより、“理解して、共に暮らしていく”という考え方が、これからの動物医療にはもっと必要になってくると感じています。そしてその始まりは、愛犬をよく観察し、よく触れて、よく話しかけてあげることから。特別なことは何も要りません。ただ、毎日の中に“気づく目”を持ってほしいと、心から願っています。
ここまで読んでくださったあなたの愛犬が、健やかに、穏やかに日々を過ごせますように。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。