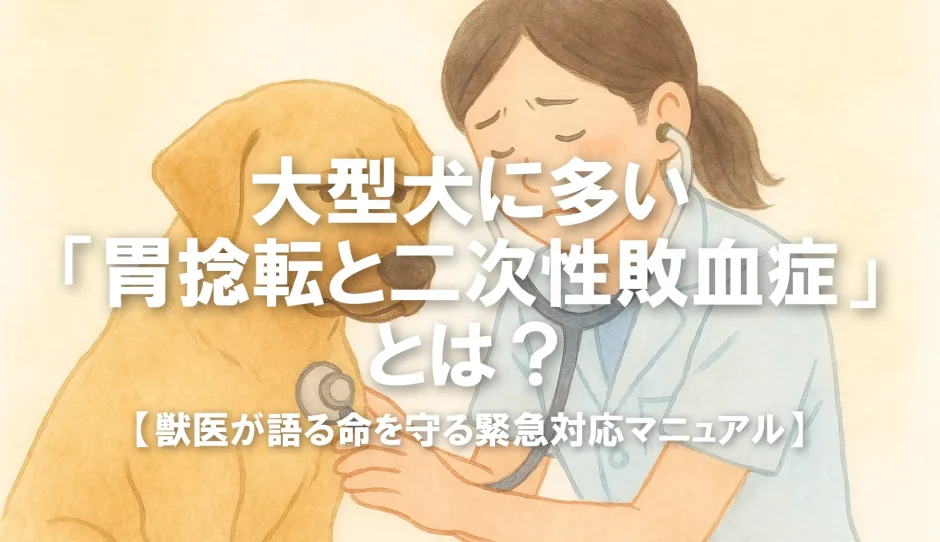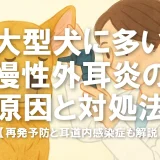大型犬に多発する「胃捻転」とは?その危険性を見逃すな
大型犬を飼っている方であれば、一度は耳にしたことがあるかもしれません。「胃捻転(いねんてん)」というこの病気は、文字通り胃がねじれてしまう恐ろしい疾患で、ほんの数時間で命に関わるケースも珍しくありません。私自身、過去に何度も緊急搬送された犬を診てきましたが、「あと30分早ければ…」と悔やむこともありました。
なぜ大型犬に多いのか?犬種と体型の関係
胃捻転が発生しやすいのは、胸の深い大型犬に多く見られます。たとえば、グレートデンやジャーマン・シェパード、ボルゾイ、バーニーズ・マウンテンドッグなどが代表的です。こうした犬種は体格の関係で、胃が回転しやすい構造になっているのです。
また、一気に大量の食事をとる習慣や、食後すぐの激しい運動もリスクを高めます。とはいえ、これらの要因が揃っていなくても発症することがあるため、日頃の観察が何より大切です。
飼い主が見落としやすい初期症状とは
この病気の怖いところは、見た目ではそれほど深刻に見えない症状から始まることです。たとえば、
- お腹がパンパンに張ってくる
- 吐きたいのに何も出ない
- 何度も立ち上がっては座るなど、落ち着きがない
- よだれがやたらと多い
- 息が浅くて早い
こうした変化は「ちょっと様子がおかしいな」と感じる程度かもしれません。でも、この“違和感”こそが重要なサインです。私がこれまで診てきた症例でも、初期に気づいてすぐ来院した子と、そうでなかった子では明暗が大きく分かれました。
胃拡張とどう違う?“ねじれ”の怖さ
一見、同じように見える「胃拡張」との違いは、胃が物理的にねじれているかどうかです。拡張だけならまだガスが抜ける余地がありますが、ねじれが加わると血管が圧迫され、胃の一部が壊死する危険性もあります。さらに悪化すると、全身に炎症や毒素がまわり、「二次性敗血症(感染性ショック)」という命に関わる事態を引き起こします。
私自身、このような緊急手術に立ち会うたびに、「予防や早期対応の大切さ」を痛感します。
次章では、胃捻転が引き金となって起こる「二次性敗血症」について、医学的な視点と実際の臨床経験をもとに詳しく解説していきます。
見過ごされがちなリスク「二次性敗血症(感染性ショック)」とは?

胃捻転の怖さは、胃がねじれること自体だけにとどまりません。もっと深刻なのは、その後に起こる「二次性敗血症(感染性ショック)」です。私が臨床で感じるのは、飼い主の多くがこの“次の段階の危険”について十分に知らされていないこと。実際、命を落とす犬の多くは、この敗血症の進行によって状態が急激に悪化していきます。
胃捻転が引き起こす体内の“ドミノ崩し”
胃がねじれると、胃壁の血流が遮断されます。その結果、組織が壊死し、腸内の細菌や毒素が血中に漏れ出すようになります。これが“二次性敗血症”の始まりです。
血中に細菌やその毒素(エンドトキシン)が流れ込むと、全身に炎症反応が広がり、血管が拡張・漏出しやすくなり、最終的には「感染性ショック」に至ります。血圧が急降下し、臓器への血流が止まり、心臓・腎臓・肝臓などが次々に機能不全に陥る──まさに命を脅かす“全身性の崩壊”が起きるのです。
臨床現場で見る“静かなる悪化”
私が印象的だったのは、胃捻転の手術後、一見落ち着いたように見えていた子が、数時間後に急変したケースです。血圧が安定していたのに、突然、チアノーゼ(粘膜の青白さ)が出始め、体温も下がり、再度ショック状態に。検査をすると、明らかにエンドトキシン反応が起きていました。
飼い主さんにとっては、「手術して助かったはずなのに、なぜまた?」という思いだったと思います。でも、それが敗血症の怖さです。手術さえすればOKではない。術後の24〜48時間が、本当の意味で“生死を分ける”時間帯なのです。
なぜ早期発見・即入院が鍵になるのか
感染性ショックまで進んでしまうと、治療は一気に複雑になります。抗生剤の投与、点滴による血圧維持、ショックコントロール、酸素投与、場合によっては人工換気…。これらはすべて時間との戦いです。
だからこそ、私たち獣医が伝えたいのは、「あれ?おかしいな」と思った時点で、迷わず病院へ来てほしいということ。躊躇しているうちに、回復率は確実に下がっていきます。
次章では、このようなリスクを少しでも避けるために、飼い主としてできる「予防」と「日常的なケア」について具体的にご紹介します。
飼い主にできる予防策と早期発見のための工夫

胃捻転および二次性敗血症は、確かに急性かつ重篤な病気です。しかし、すべてのケースが防げないわけではありません。むしろ、日々の食事管理や生活習慣の見直しでリスクを軽減することは可能です。私がこれまで診てきた犬たちのなかでも、「予防意識の高い家庭」で暮らす子は、重症化を免れている例が多くありました。
食事回数と量を見直す
まず見直したいのが食事の与え方です。特に注意すべきなのが、一日一回の大量の食事。これは胃に一気に負荷がかかる原因となり、胃捻転の引き金になります。私が推奨するのは、1日2〜3回に分けて、少量ずつ与えること。
また、早食いの癖がある犬には、食器を工夫するだけでも違いが出ます。たとえば「スローフィーダー」を使用すれば、急激な胃の膨張を抑えることが可能です。
食後の運動は厳禁
食後すぐに走り回るクセのある犬も要注意です。特に若くて活発な犬に多いですが、食後30分〜1時間は安静に過ごすことが大切。私の知っている家庭では、食後にクレートに入れて強制的に落ち着かせることで、発症リスクを下げていました。シンプルですが、効果的です。
毎日の「小さな変化」に気づくことが最大の予防
胃捻転も敗血症も、最初はごく軽微な変化から始まります。飼い主が「うちの子、今日は少し元気がないかも」「呼吸が浅いかも」「お腹が膨れてる気がする」といった、違和感に気づけるかどうかが生死を左右します。
私がかつて診たある症例では、飼い主が「なんとなく目つきがぼんやりしている」と感じて、即座に来院した結果、まだ軽度の胃拡張の段階で対応でき、事なきを得ました。愛犬の“いつも”を知っているのは、獣医よりも飼い主です。だからこそ、小さな変化に敏感であることが、最大の武器になります。
次章では、もしもの時に迷わないために知っておきたい「動物病院での対応と治療の流れ」について、現場の視点から詳しく解説します。
緊急時に慌てないために知っておくべき治療の流れ

胃捻転とその合併症である二次性敗血症。このコンビは、まさに“静かなる脅威”です。目の前で苦しむ犬を前に、「もっと早く運ばれていれば…」と胸を締めつけられたことが、一度や二度ではありません。飼い主さんが冷静に動けるかどうかは、命を救う大きな分かれ道。だからこそ、ここでは“実際に病院で何が行われるのか”を、あらかじめ知っておいてほしいのです。
1. まず行うのは「命をつなぐ応急処置」
胃捻転が疑われる犬が搬送されてくると、私たち獣医が真っ先に取りかかるのは、状態の安定化です。呼吸はどうか、心拍は? 血圧は保たれているか? これらを数分単位で確認しながら、点滴で循環を支え、酸素を与える処置を行います。
この段階での遅れが、麻酔のリスクを一気に高めます。経験上、ショック状態での全身麻酔は非常に危険で、正直言って“賭け”に近い部分があるのです。だからこそ、術前のこの処置が生死の分かれ目になります。
2. レントゲンと血液検査で「状況を見極める」
応急処置が進むなかで、レントゲン撮影を行います。胃がねじれていれば、X線上で“くっきりとした境界線”のような異常が見えることが多く、経験のある獣医師ならほぼ一目で判断がつきます。
並行して行う血液検査では、特に乳酸値を重視します。これは組織の酸欠や壊死を反映する数値で、敗血症の兆候をつかむ鍵となります。私の印象では、乳酸値が極端に高い犬は、その後の経過が厳しいことが多い印象です。
3. 手術の実際──ただ戻すだけでは終わらない
胃捻転と診断が確定したら、即手術です。ねじれた胃を正しい位置に戻し、壊死していないかを目視で確認。必要に応じて壊死した部分を切除します。ときに脾臓の摘出が必要になることもあります。
そして忘れてはいけないのが、「胃固定術(胃を腹壁に縫い付けて再発を防ぐ処置)」です。私は、再発の不安を少しでも取り除いてあげたいという思いから、ほぼ全例でこの処置を行っています。
4. 術後こそ“真の峠”
手術が終わっても、戦いは終わりではありません。むしろ、ここからが本当の勝負です。なぜなら、胃捻転によって一度ダメージを受けた体は、術後に全身性炎症反応(SIRS)や感染性ショックを引き起こすリスクを抱えているからです。
ICU管理下での持続点滴、抗生剤、血圧コントロール、酸素投与──それらすべてが“当たり前”の治療になります。私は常に、「術後24時間は一睡もしない覚悟で見守るべき」と自分に言い聞かせています。それほど繊細で、予断を許さない時間帯なのです。
次章では、そんな緊急時に備えるために、飼い主ができる「準備」や「チェックリスト」について、具体的にお伝えします。
万が一に備えて、飼い主が今からできること

獣医として、私は常に「もっと早く連れてきてもらえたら…」という場面に向き合ってきました。胃捻転も、敗血症も、早期対応こそが唯一の防御策です。けれど、いざというときに冷静に行動するには、日頃からの“備え”が欠かせません。ここでは、飼い主が今すぐ始められる具体的な対策と心構えを、現場の視点からお伝えします。
1. 緊急時の行動フローを家族で共有する
犬が突然苦しみ始めたとき、最も大事なのは“判断と行動の速さ”です。特に深夜や休日に起きた場合、「どこの病院が対応してくれるのか」「何時まで診療しているのか」を調べているうちに、命のタイムリミットが迫ってしまうことも。
私が飼い主さんにいつも伝えているのは、「緊急時マニュアル」を作っておくこと。たとえば、
- 通える範囲の24時間対応病院のリスト(住所・電話番号)
- 自家用車での移動時間の目安
- かかりつけ医に緊急時の紹介先を確認しておく
こうした情報を、冷蔵庫やスマホに貼っておくだけで、いざというときの行動が格段に早くなります。
2. 「うちの子専用チェックリスト」を作ろう
胃捻転の前兆は、犬によって微妙に異なります。ある子は「えづき」が目立ち、ある子は「ぼーっとした表情」がヒントになることも。だからこそ、「うちの子はこういう時に体調を崩しやすい」「食後にこういう行動をすると要注意」といった、“その子だけのサイン”を家族で共有しておくことが大切です。
私の患者さんのなかには、こうした日々のメモをLINEグループで共有しているご家庭もあります。ちょっとした変化を見逃さない習慣が、結果として大きな命の分かれ道を救うのです。
3. 動物病院の選び方を見直す
いざというときに頼れる病院を選ぶことは、ペットを守るうえでの“命綱”です。診療時間や設備だけでなく、「どんな対応をしてくれるか」「飼い主の不安にどれだけ寄り添ってくれるか」といった点も重要です。
実際、手術が必要なケースでは、麻酔科医やICU設備が整っている施設のほうが安心感があります。信頼できる主治医と、万が一の時に紹介してもらえる連携病院の体制があれば、いざというときの不安が大きく減ります。
最終章では、この記事全体を通して私が伝えたかった「命と向き合う現場の想い」について、獣医師としての率直な気持ちを綴ります。
命と向き合う現場で、私が本当に伝えたいこと
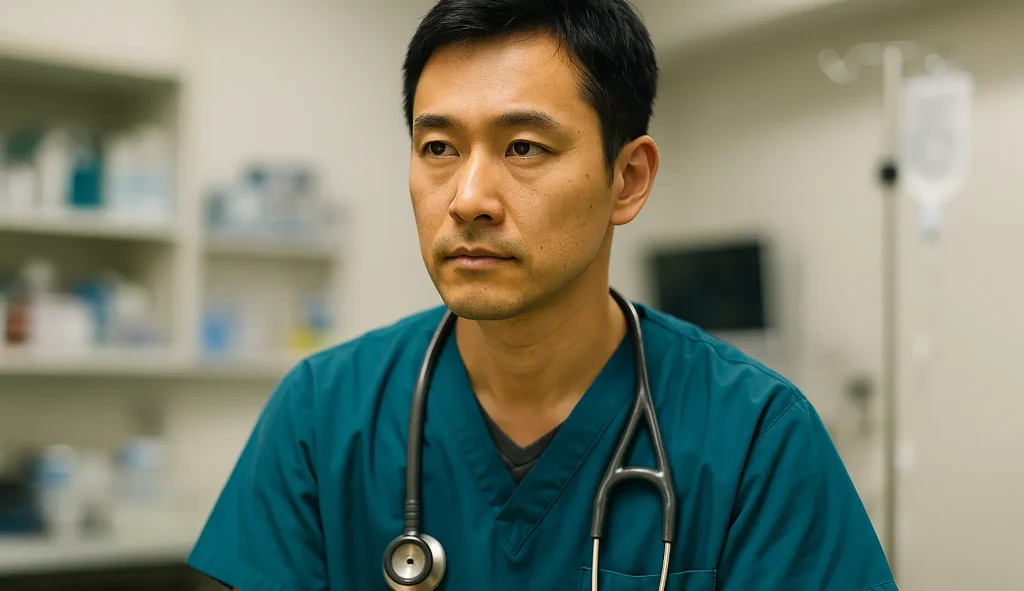
胃捻転、そしてそれに続く二次性敗血症──。これほどまでに、発症からの“時間”が結果を左右する疾患はそう多くありません。ほんの数時間前まで元気に走り回っていた犬が、わずか数時間で命を落とす現実に、私は何度も向き合ってきました。
このテーマを選んで執筆したのは、ただ知識を伝えたかったからではありません。“一緒にいた時間を後悔してほしくない”──それが私の心からの願いです。
獣医である前に、ひとりの「動物好き」として
私は獣医として日々多くの症例に向き合っていますが、動物たちを“命ある存在”として敬う気持ちは、開業したばかりの頃から変わりません。だからこそ、目の前の小さなサインにもっと早く気づいてあげられれば、救えた命があったのではないかと、自責の念に駆られることもあります。
けれど、すべての飼い主が獣医のような知識を持つ必要はありません。ただ、「何かおかしい」と思ったときに、その違和感を信じて、すぐに行動に移してほしい。それだけで、救える命は確かにあるのです。
飼い主と獣医が“チーム”になれる社会へ
医療は、獣医師だけでは完結しません。飼い主さんの判断、観察力、そして「うちの子を守りたい」という愛情が、最大の治療になります。
私はこれからも、単なる診療や手術の繰り返しではなく、飼い主さんと一緒に考え、選択し、歩んでいく“チーム医療”の形を目指していきたいと思っています。その第一歩が、こうして知識を共有する場だと信じています。
この記事が、あなたとあなたの大切な家族の命を守る“きっかけ”になることを、心から願っています。
お読みいただき、ありがとうございました。
もしこの記事が少しでも役に立ったと思ったら、周囲の飼い主仲間にもシェアしていただけると嬉しいです。知識は、行動に移されてこそ、命を救う力になります。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。