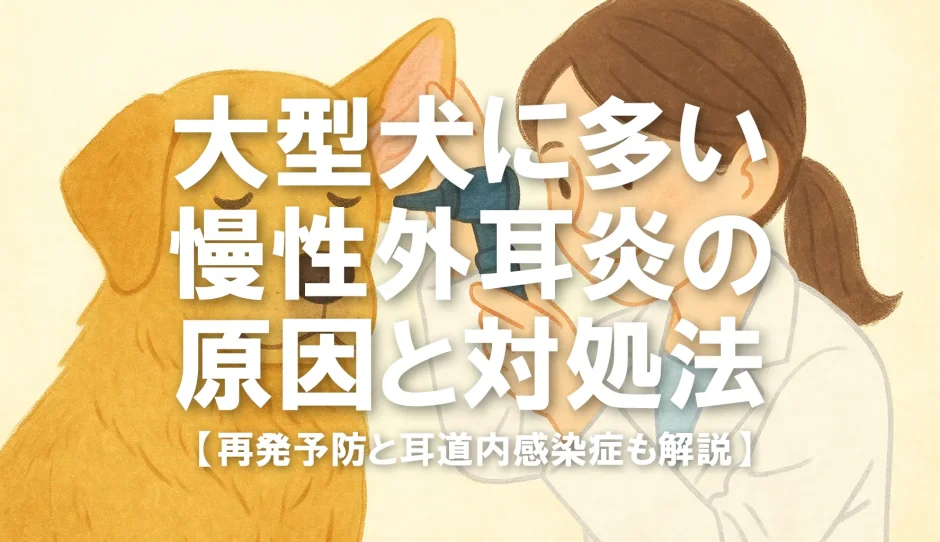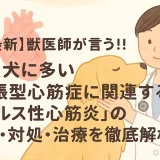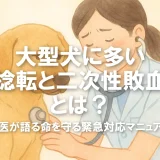大型犬の“耳トラブル”はなぜ起きる?~慢性外耳炎の正体~
大型犬と暮らしていると、一見些細な「耳のにおい」や「かゆがる仕草」に気づくことがあります。私自身も大型犬を飼っていた経験があり、最初は「遊びすぎて耳が蒸れたのかな」程度に考えていました。しかし、それが慢性外耳炎や耳道内の感染症の始まりだったことを、後から思い知ることになったのです。
外耳炎とはどんな病気?
外耳炎とは、耳の穴から鼓膜までの「外耳道」が炎症を起こす状態を指します。耳が垂れている犬種や、耳毛が多い犬は特に通気性が悪く、炎症を起こしやすい傾向にあります。なかでも大型犬は耳の構造上、湿度がこもりやすく、病気の温床になりやすいのです。
なぜ大型犬に多いのか?
私がこれまで見聞きした限りでも、ラブラドールやゴールデン・レトリバーなどは慢性的な耳トラブルを抱えていることが多く、下記のような特徴が共通していました。
- 耳道が深くて複雑なため、汚れや湿気がたまりやすい
- 頭が大きく皮脂の分泌も多いため、真菌が繁殖しやすい
- イヤーケアが難しく、気づいたときには炎症が進行している
これらが重なると、一度炎症を起こすと治りにくくなり、「慢性化」の悪循環に陥りやすくなります。実際、治ったと思ってもすぐ再発するケースも多く、飼い主にとっては非常に根気のいるケアが求められます。
見過ごされがちな初期サイン
外耳炎がやっかいなのは、初期段階では犬がそれほど苦しんでいないように見えることです。飼い主が気づかないまま進行し、気づいたときには耳道が腫れ、分泌物が増え、治療も長期戦になります。たとえば、以下のような症状は要注意です。
- 頭をぶるぶる振る
- 耳を後ろ足でかく
- 耳垢が茶色や黒っぽい
- 耳の中が赤くなっている
- 耳を触ると嫌がる、あるいは怒る
こうした行動を見かけたら、単なる“癖”や“汚れ”として見逃さないでください。少しの違和感が、慢性疾患の入口になっていることもあります。
次章では、耳の中でどのような変化が起こっているのか、慢性化する背景やメカニズムを掘り下げていきます。耳の病気は「見えにくい」ぶん、早期発見が本当にカギを握ります。自分の愛犬を守るために、正しい知識を持っておくことが何よりも大切だと、私は強く感じています。
なぜ治らない?慢性外耳炎が繰り返す理由と“見えない悪循環”

「何度治療してもすぐに再発してしまう」——これは大型犬の外耳炎によくある悩みです。かくいう私も、何度も動物病院に通った末に「慢性外耳炎」の厄介さを痛感しました。薬をつければ一時的に良くなる。でも、また数週間でかゆがり、耳垢がにおう…それは単なる治し方の問題ではなく、“耳の中で何が起きているか”を理解しないと、本当の意味で改善には向かいません。
大型犬特有の耳の構造が落とし穴に
大型犬の耳道は、構造的に深く、L字に曲がっていて、しかも皮膚の面積が広く蒸れやすい。これが外から見ても分からない部分で、炎症を長引かせる原因になります。
たとえば、耳の表面だけを拭いても、耳道の奥に残った分泌物や菌はそのまま。私が過去に見た症例でも、「外はきれいなのに中が真っ赤」という犬が少なくありませんでした。見た目に騙されず、耳の奥を意識したケアが必要だと感じた経験です。
マラセチアと細菌がつくる“悪環境”
慢性外耳炎の背景に多いのが、「マラセチア」という酵母菌。これは健康な皮膚にも存在する常在菌ですが、湿気や皮脂が多くなるとバランスが崩れ、異常繁殖を起こします。耳がべたつき始める頃には、すでにマラセチアの数が増え、そこに細菌まで加わると炎症は一気に悪化します。
私が担当した中でも、耳のにおいが「酸っぱい」と表現される犬はたいていこのパターン。耳垢の色や質感の変化に気づいたら、すでに炎症が進んでいるサインと考えた方がいいでしょう。
飼い主の行動が“慢性化”を助長している?
少し厳しい言い方になりますが、慢性外耳炎の背景には飼い主の無意識な行動が関与していることもあります。以下に、実際によく見られるケースを挙げてみます。
- 耳掃除をやりすぎる:炎症がある状態で綿棒や洗浄液を多用すると、耳道の皮膚を傷つけ、さらに悪化させます。
- 治療を途中でやめる:「かゆがらなくなったから大丈夫」と薬を中止すると、奥に残った菌が再び繁殖します。
- 市販薬での自己判断:合わない薬を使うと、かえって菌が強くなって再発しやすくなるリスクもあります。
私自身も、「良かれと思っていた行動が裏目に出る」経験を何度もしました。耳のケアは、見た目の改善ではなく、“中で何が起きているか”に意識を向ける必要があるのです。
耳のトラブルは、犬にとってもストレスの原因になります。痒みや痛みはもちろん、寝つきが悪くなったり、イライラしたり、性格まで変わってしまうこともあるほどです。
だからこそ、「またか…」で済ませず、繰り返す根本原因にしっかり向き合うことが何より大切だと、私は強く思います。
次章では、動物病院では実際にどのような診察や治療が行われているのかを詳しくご紹介します。市販のケアでは限界があるからこそ、プロによる判断の重要性を改めてお伝えしていきます。
動物病院での診察はどう進む?慢性外耳炎の正しい治療フローとは

耳をかゆがる、独特なにおいがする、耳垢が増えた…そんなとき「とりあえず拭いておこう」と思った経験、私にもあります。でもそれは、あくまで“応急処置”でしかありません。慢性外耳炎は見た目以上に根深い病気。放っておけば中耳や内耳にまで進行し、治療が長期化してしまうこともあるのです。
耳の奥で何が起きているか、まずは“見る”ことから
動物病院に連れていくと、最初に行われるのが耳鏡(じきょう)を使った耳道の観察。これが、いわば治療の“起点”になります。外から見ただけでは判断できない奥の腫れやただれ、膿のたまり具合まで、細かく確認されます。
私が印象的だったのは、耳の入り口はきれいなのに、奥がひどくただれていたというケース。見た目では分からないからこそ、こうした専門的な検査がどれほど大切か、改めて痛感しました。
原因菌を“見極める”耳垢検査の重要性
耳の中が炎症を起こす原因は一つではありません。マラセチアという真菌(酵母菌)が異常繁殖していることもあれば、細菌感染を伴っていることもある。だからこそ、採取した耳垢を染色し、顕微鏡で確認する検査は必須です。
あるとき、何度薬を変えてもよくならなかった犬がいて、原因が実は耐性菌だったことが検査でわかったことがありました。この経験から、「薬が合っていない」と感じたら、すぐに再検査をお願いすることの大切さを、私は飼い主さんにも伝えたいと思うようになりました。
治療は“見えないケア”の積み重ね
治療が始まると、まず耳道の洗浄が行われます。これは汚れを取るためだけではなく、薬がきちんと患部に届くようにするための大事なステップ。洗浄後には、炎症や感染の程度に応じて、抗生物質や抗真菌薬、時にはステロイドを含んだ点耳薬が処方されるのが一般的です。
重症例や再発を繰り返す場合は、内服薬が併用されることもあります。ただ、ここで忘れてはいけないのが「治ったように見えても途中でやめない」ということ。私は過去に、良くなったからと自己判断で治療をやめてしまい、結果的に前より悪化させてしまったことがあります。
飼い主と獣医師の“連携”が成果を生む
慢性外耳炎の治療は、単に薬を使うだけでは終わりません。日々の観察、適切なケア、異変の早期発見。それらを支えるのは、まぎれもなく飼い主の存在です。
私がこれまでに見てきたなかでも、症状の改善が早い犬の多くは、飼い主がまめに耳の状態を記録し、疑問点をすぐに相談するような“連携”が取れていました。治療の主役は獣医師かもしれませんが、実行するのは家庭。だからこそ、両者の連携は“チーム医療”そのものだと、私は感じています。
慢性外耳炎は、短期間で完全に治る病気ではありません。むしろ、時間をかけて付き合っていく姿勢こそが、結果的に犬の生活の質を高めることにつながります。
次章では、病院での治療だけでは防げない“家庭での耳ケア”について、私の経験をもとに具体的な方法をご紹介します。再発予防のカギは、実は毎日のほんの小さな行動の中にあるのです。
再発予防は“日常”の中にある──自宅でできる耳ケアと生活環境の見直し

慢性外耳炎と向き合ううえで、病院での治療はもちろん重要ですが、それだけでは十分ではありません。むしろ本当の勝負は、家に帰ってからの日常生活にあると私は考えています。犬の耳は、とても繊細で、ちょっとした湿気や皮脂の変化でトラブルを起こすこともある。だからこそ、日頃のケアや環境づくりが、再発を防ぐうえで大きな意味を持つのです。
耳掃除は“頻度”より“目的”が大事
耳掃除というと、「とにかく清潔にすればいい」と思われがちですが、それは大きな誤解です。むやみに掃除をしすぎると、耳の中のバリア機能を壊してしまい、かえってトラブルを招きます。
私自身、以前は耳垢を見つけるたびに綿棒で取っていましたが、それが悪化の原因だったことに気づいたのは、かかりつけの獣医師に「今すぐやめて」と言われてからでした。今では、症状がないときは週1回、耳の入り口を軽く拭く程度にとどめています。耳の奥は、獣医師の指示がない限り、下手に触らない方が無難です。
湿気対策は“見えない工夫”がものを言う
垂れ耳の大型犬は、耳道の通気が悪く、蒸れやすいという構造的なリスクを抱えています。そのため、日常的に耳周辺の湿気をコントロールする工夫が欠かせません。
たとえば我が家では、散歩や水遊びのあと、耳の根元をタオルで軽く押さえて水気を取り、その後にドライヤーを弱風で当てています。これを始めてから、耳垢のベタつきが目に見えて減りました。毛量の多い犬種なら、耳周りの毛を少し短く整えておくのも効果的です。
フードやアレルギーとの関係を見直す視点を
「耳のトラブルと食事?」と意外に思うかもしれませんが、私が見てきた中には、フードを変えたことで耳の状態が改善したケースも少なくありません。特に、特定のタンパク源や穀物に対するアレルギーが原因となっていることもあるため、気になる症状が続く場合は、食生活もチェックしてみる価値があります。
実際、愛犬に低アレルゲンフードを試してみたところ、それまで何度も繰り返していた耳の赤みが落ち着いたという経験があります。もしも耳のトラブルが慢性的に続いているなら、「食」が関係している可能性も、選択肢のひとつとして視野に入れてみてください。
ストレスケアが“耳”を救うこともある
犬の耳の不調とストレスが無関係ではないことも、個人的には非常に実感しています。長時間の留守番、運動不足、飼い主との関係性の変化など、犬にとっての“精神的な刺激”が、免疫バランスを崩し、皮膚や耳のコンディションに影響を与えてしまうこともあるのです。
私の場合、毎日の散歩ルートを日替わりで変えたり、週に数回は新しいおもちゃを取り入れたりすることで、愛犬のストレスサインが減ったと感じています。耳だけを見つめるのではなく、犬の心と身体をトータルで見ることの大切さを、改めて痛感しています。
慢性外耳炎に終わりはありません。でも、付き合い方を知れば、管理はできます。そしてその鍵は、日々の小さな行動や工夫の中に隠れています。
次章では、外耳炎とよく似た症状を持ちながらも、より深刻になりやすい「耳道内感染症」について掘り下げていきます。似ているからこそ、見落としやすい違いに、ぜひ注目してください。
外耳炎と見分けがつきにくい「耳道内感染症」──見落としがちな危険信号とは

耳のにおいやかゆみ、耳垢の増加といった症状が出ると、多くの飼い主が「いつもの外耳炎だろう」と考えがちです。かつての私もそうでした。市販の耳洗浄液で様子を見ていたものの、なぜか治らず、むしろ状態が悪化。動物病院で診てもらったときには、すでに“外耳”の問題では済まされない状況になっていました。
ここでは、外耳炎と非常によく似た症状を持ちながら、より深刻な「耳道内感染症」について解説します。早期発見のカギは、“耳以外”に現れる小さなサインに気づけるかどうかです。
外耳炎との違いは「炎症の深さ」
外耳炎は、耳の入り口から鼓膜までの「外耳道」に起こる炎症です。一方で耳道内感染症は、そのさらに奥、鼓膜の内側や中耳、場合によっては内耳にまで炎症が波及した状態を指します。
私が関わったある大型犬では、耳をかゆがるだけでなく、急に首をかしげたまま戻らなくなり、歩き方まで不安定になっていました。結果として診断されたのは、中耳炎。つまり、すでに外耳を超えて感染が広がっていたのです。
見極めのポイントは“耳以外の異変”にある
耳道内感染症を見抜くには、耳そのものの症状に加えて「全身の変化」に目を向けることが必要です。以下のような様子が見られたら、ただの外耳炎ではない可能性を疑うべきです。
- 頭を傾けて固定するような仕草を続けている
- 片側だけを気にして耳を触らせない
- ふらつく、まっすぐ歩けない
- 顔面の片側だけが動きにくくなる
- 食欲が落ちたり、ぐったりして元気がない
これらの症状が見られる場合、単なる皮膚炎ではなく、内耳や神経系に影響が及んでいる可能性があります。私の場合、こうした異変に気づけたのは、愛犬の「いつもと違う目の動き」に注意したからでした。
精密検査でしか見つからない病変もある
外耳炎であれば、耳鏡や綿棒での耳垢チェックである程度診断がつきます。しかし、感染が耳道の奥に及んでいる場合、肉眼では限界があります。レントゲンや超音波、さらに詳しく調べる場合はCT・MRIといった画像検査が必要になることもあります。
もちろん費用や時間はかかりますが、「なんとなく治らない」を繰り返すよりも、一度しっかり原因を突き止めるほうが、結果的に治療も早く進むと私は思っています。
放置すれば生活の質にも大きな影響が
耳道内感染症を見逃し続けると、やがて顔面神経の麻痺やバランス障害、慢性的な痛みや不快感が残ることもあります。最悪の場合、聴力の低下や完全な失聴につながるケースもあるとされています。
実際に、片耳が聞こえづらくなってしまった犬を見たことがあります。その子は音への反応が鈍くなり、コミュニケーションも取りづらくなってしまったのです。耳の病気が、これほどまでに犬の“日常”を変えてしまう現実に、私は強い危機感を覚えました。
耳の異常は、見た目や耳垢の量だけでは判断がつかないことがあります。だからこそ、「ただの外耳炎だろう」と決めつけるのではなく、少しでも違和感を覚えたら早めに獣医師に相談してほしい――それが私の本音です。
次章では、慢性外耳炎や耳道内感染症という難しい病気と、どう前向きに向き合っていけばいいのか。この記事全体を通して私が感じたことを、飼い主としての視点で綴ります。病気との付き合い方を見つめ直すヒントになれば幸いです。
慢性外耳炎と向き合って――犬とともに歩む飼い主の覚悟

この記事をここまで読んでくださった方は、きっと愛犬の耳の不調に悩んでいたり、再発を繰り返す慢性外耳炎に不安を感じている飼い主さんだと思います。私自身もそうでした。何度も治療しては再発し、そのたびに「またか…」と肩を落とし、愛犬のかゆがる仕草を見るたびに、やるせない気持ちになったものです。
けれど、あるとき気づいたんです。慢性外耳炎は「完全に治すもの」ではなく、「うまく付き合っていくもの」だと。そこから私の向き合い方は大きく変わりました。
“治す”から“管理する”という考え方へ
外耳炎や耳道内感染症は、一度慢性化すると完治が難しいケースも多くなります。でもそれは、絶望ではありません。日常的なケアと定期的な診察を組み合わせることで、「症状を抑えて快適に過ごす」ことは十分に可能です。
私も、「今月は耳がきれいだったね」と獣医師に言われたときの安堵感は、何よりのご褒美でした。完治だけをゴールにするのではなく、日々の小さな安定を積み重ねることが、犬と飼い主、双方の心を軽くすると思います。
“面倒”ではなく“愛情”として向き合う
正直、耳のケアは手間がかかります。点耳薬を嫌がる子もいるし、耳を触られるのが苦手な犬だってたくさんいます。私も最初の頃は、毎日の耳掃除や薬の投与がプレッシャーでした。
でもある日、ふと気づいたんです。これって全部、犬の「痛い」「かゆい」「つらい」を減らしてあげるための行動なんだと。それに気づいてから、ケアの時間は“お世話”から“コミュニケーション”に変わりました。
今では、薬をつけたあとに「よく頑張ったね」と頭を撫でながら過ごす時間が、私たちにとって小さな絆の時間になっています。
獣医師と“並走する意識”を持とう
耳の病気は、見えにくいからこそ判断が難しい。だからこそ、獣医師との信頼関係は欠かせません。私は、疑問があれば些細なことでもすぐに聞くようにしていますし、経過をメモに残して相談材料にすることもあります。
「獣医に任せる」のではなく、「一緒に解決していく」という姿勢が、愛犬の健康を守るうえで何よりも大切だと感じています。
耳のトラブルは繰り返すもの。でも、知識があれば慌てずに対応できます。そして何より、“完璧な耳”を目指すのではなく、“その子にとっての快適”を一緒に目指していく――それが、飼い主にできる最大の愛情表現ではないでしょうか。
この記事が、悩める飼い主さんの一歩を後押しするきっかけになれば、私としても本望です。どんなに小さなことでも、今日からできるケアがあります。愛犬の耳に、そして心に、優しく寄り添っていきましょう。
当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。